
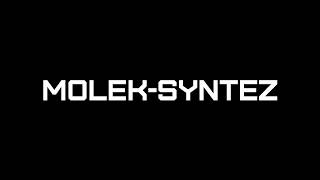





Molek-Syntez
Molek-Syntez を使用すると、ルーマニアの小さなアパートで快適に、さまざまな薬理学的効果を持つ小分子を作成できます。
みんなのMolek-Syntezの評価・レビュー一覧
syshoji_666

2023年08月01日
[h1]超高難易度アルゴリズムゲー!!(脳死)[/h1]
同メーカーの『Opus Magnum』『Spacechem』と似たようなアルゴリズム生成ゲームです。これらは「与えられた物質を操作し、求められた物質を生成する」という部分が共通していますが、分子を飛ばしたりくっつけたりするのが直感的に理解し難く、個人的には3つの中では本作が一番とっつきにくいと思います。UIの無骨さも人によっては「ウッ」となるかもしれません。同メーカーのプログラミングゲーム『TIS-100』よろしく要らんことはあまり何も言ってくれず、前に進める者だけが進めというハードコア仕様のためチュートリアルすらうまくいかない方も多いのではなかろうかと思います。まあ一度理解してしまえば割と簡単なので『Opus Magnum』『Spacechem』にハマれた方で、もっとハードコアなパズルゲームでも構わんよ、という方はトライしてみると良いのではないでしょうか。Zachお決まりの特殊ルールソリティアも収録されており、こちらもやや難しめですがコツを掴んでしまえばスイスイとクリアできます。
通常モードは10時間程度でクリア、Extraキャンペーンの幾つかのソリューションは大変難しく煮詰まっています。回路作成とか、アルゴリズム構築とか、プログラミング的な素養がある方なら割と無理なく楽しめるかと思います。
近未来ディストピア的なストーリーは陰鬱で、BGMもなく、重たい雰囲気のゲームですが、まあZachフリークスの諸氏はそんなものはお飾りかと思いますので、ハードコアなパズルで脳に負荷をかけたい!という方は是非どうぞ。
MikenekoTaro

2021年06月07日
Opus MagnumよりThe Codex Of Alchemical Engineeringに操作が近い印象を受けました。もちろんアームはないですが、エリアと命令数が限られているため、omの生成された黄金の最小面積解や万能溶媒の最速解のような滅茶苦茶な労力なく上位%を取れます。ワークショップがないのとストーリーを見返せないのが寂しいですが、限りあるステージで上位%以上を狙っていくのも悪くないですね。
一番困ったのは左右移動の命令がどうも直感と逆向きに思える点。幸いZachらしく試運転→再設定がすぐにできるので致命的なミスには繋がらなかったですが、始終小骨が引っかかる思いで解いていました。また、結合様式の決定機構が未だに掴めていません。原子の配置や元基の結合次数、さらには水素原子を打ち込む位置まで結合様式に影響するようで、ここは研究の余地がありまだまだ楽しめそうです。
Minamina

2020年06月28日
〇90年代サイバー世界風味の無機質な分子工学パズル。
〇良い点:
・有限だが豊富な数の問題集と自由な解法。
・回答時に自分がどの位置なのかグラフで表示されるので、最適解を探そうとすると沼。
・シンプルな作りで直感的でわかりやすい。
〇悪い点:
・ランダム生成が無く同じような問題ばかりで飽きる。
・最終的にどんな形であれ提示された形になればいいので、ぐちゃぐちゃでも問題が解ける。
・UIが初見で分かりづらい上に、独特な言い回しの英語で何が言いたいのか分からない。
〇総評:
初見でプレイヤーを突き放すスタイルのゲームなので、理解力がないと最初の画面で躓くので注意。
YouTube等で日本人がアップロードした日本語解説があるので、そちらを見るなり調べたりするのをお勧めする
日本語化できなかったり、ユーザーを突き放したUIで嫌厭してしまうが、
一度やり方さえ理解できれば、英語が読めなくても最後まで問題は解けるし、
サイバーな雰囲気にも浸れるので、英語のままでもお勧め。
shibacho

2020年06月03日
とりあえず表面クリア。
他のZachtronics のパズルゲームの中でも地味だし、ユーザー作成問題機能も今の所なし
UIはこなれているので思い通りに動かしづらいというフラストレーションはたまらないのが良いところ。
これをやるならOpus Magnum か SpaceChemを先にやることをオススメするが、Zachtronics マニアなら抑えておいてもいいかも
Gacky

2020年05月17日
Zachtronicsの他のゲームは面白かったのだが、これに関してはお勧めできない。
問題が解けても爽快感が無く、白黒のUIも味気ないだけで利点を感じられない。
ウィッチ(?)

2020年04月03日
パズルは・・・まあ普通かな、平面でしか弄れないのが残念なポイント
しかーし、このゲームのメインはケミカルを弄ることではなくカードゲームにある
変則ルールのソリティアを100回クリアすることにこそ、このゲームを遊ぶ本当の理由なのだ
akarregi

2019年12月20日
(まだ半分しか突破できてないけど、面白いのでレビューします・ゲームプレイにはあまり触れてません)
[b]2092年[/b]の12月。ルーマニア・クルジュ=ナポカ。……の一化学者。
分子合成装置(MOLEK-SYNTEZ)を使ってヤバい薬物を作ろう!
...とはいったものの、いつもの Zachtronics なのでそう簡単にやれるものではありません。とはいえ The Codex of Alchemical Engineering とか Opus Magnum をプレイしていればとっつきやすく、初見でも重要な動作はなんとなくわかるインタフェースは流石。
さて、分子を合成するわけですが……最初は過酸化水素とかエタノールなのでまだ良さそう。しかし途中でクロロホルムとかが出てきて雲行きが怪しくなってきて、遂には(日本の法令上)麻薬な薬物も出てきます。ケタミンとかメスカリンとか。大丈夫なのか私は。何故、[b]ルーマニアのクルジュ=ナポカ[/b]でこんなものを合成せにゃ……おっと。あまり詳しく言うとネタバレなので、以下略。華強北でよくわからないアセンブリ組むのとどっちがいいんだろう?
別角度から見てみると、起動と終了演出が非常に TIS-100 っぽい。起動ログみたいなのも出てくるし雰囲気があります。SHENZHEN I/O なんかは現代的だけど、こういうレトロなものも味があって中々。完全に白黒なのもまた TIS-100 っぽい。Opus Magnum が SHENZHEN I/O のカウンターパートなら、こちらは TIS-100 のカウンターパートなんでしょうか。
皆様の期待通り、恒例のソリティアもある。ただ……これ……非常にルールがキm……そう、奇特すぎてインストラクションなしでクリアはまず無理でしょう。まず札が(普通のトランプで言う K → A 順に)T, K, D, V, 10, ..., 6。更にはチートして普通置けないところにカードを置けます。後は概ね普通のソリティアです。これがルーマニアン・ソリティア。やべえよ……
さて、2092年のとんでもない化学を味わいたい方。是非クルジュ=ナポカで MOLEK-SYNTEZ を体験してみてください。パズルゲー無理だって人も、全クリ目指さないで雰囲気を味わうのも全然ありだと思います。そして、パズルゲーが好きな方。もう買ってますよね……?
APM

2019年12月10日
メインキャンペーンのクリアまでプレイ。
プログラミングチックに命令を組み合わせて課題を達成するタイプの、いつものZachtronics製パズルゲーム。材料に手を加えて目標の薬物を作ることが目的だが、今作の特徴は、スタートとなる材料を複数の選択肢から自分で選べること。それによって解く過程やスコアも変わってくるため、計画性が求められる。
Opus Magnumとは違い並べられる命令数に制限があるが、メインキャンペーンをクリアするだけなら難易度はそれほど高くない(一部のステージを除く)。ステージごとに新たなひらめきが求められるような感覚にはやや乏しく、解き心地は若干単調に感じられた(その点はSpacechemがあまりに素晴らしかったので、ハードルは上がっている)。材料の選択システムといい、今作は最適化の楽しみに重点を置いているのかもしれない。
一つ気になったのは、「複数の結合パターンがあり得るような原子の配置になった時、どれになるのか」がはっきりしない点。望ましくない結合が成立しないよう工夫する必要があるのだが、何もしなくても望み通りの結合が出来てしまうこともある。実際には法則はあるのだが(クリア後に調べました)ゲーム内では明示されておらず、プレイ中にはモヤモヤした気持ちになる。
一応申し訳程度のストーリーはあり、日本語化はされていないが、本当に申し訳程度の要素なのであまり気にしなくてよい。フレンドとスコアが競えるので、お友達と一緒に遊ぼう!
saga

2019年11月15日
OpusMagnumのシステムとSpaceChemの化学要素とTIS-100の見た目を融合させた、いつもの変態パズルゲーム。
材料となる分子に水素原子を付けたり吹き飛ばしたりして、課題の分子を合成するのが目的。
材料にする分子はカタログの中から好きなものを選んで使うことができる。(12種類ある)
この入力が選べるというのはこれまでのシリーズにない新要素で、これのせいで考えうるパターンが増大する。
クリアするだけなら簡単?だけど、ハイスコアを目指そうとするとクソ難しいタイプ。
Spooky

2019年11月06日
スコア 95/100
Zachtronics のロジック作成パズルゲーム。現在(2019/11/07)、アーリーアクセスだが、ストーリーとソリティアミニゲームを含む完全なキャンペーンとのこと。
謎のヴィジュアルノベル『Eliza』に浮気していたときはどうなるものかと思っていたが、無事パズルゲームの新作をリリース。コンスタントに新作を出してくれるのでとてもありがたい。
ゲームの内容的には過去の作品だと『Opus Magnum』に似ている。ただ『Opus Magnum』であった伸縮アームはなくなっているので、力業に任せたインチキな解法はできなくなっている。
難易度は今のところ不明で、やや簡単かもしれない。ソリティアも完備しているようなので、パズルで疲れたら息抜きにソリティアも良いと思う。ゲームはストイックなパズルゲームで、言語依存はほぼ0。
ロジックの作成もアイコン化されているパーツを組み合わせるだけなのでほとんどの人が問題無くプレイできると思う。
今のところ、超面白い。コレを待っていた! さすが Zachtronics という完成度。
パズル好きならあり。
HAC

2019年11月06日
[h1]ファーストインプレッション[/h1]
[url=https://store.steampowered.com/app/558990/]Opus Magnum[/url] をよりシンプルにしたものという印象を持っていたのですが、ちょっと違いますね。インターフェイスこそ似通っていますが、このゲーム独自の制約がいくつかあって、最適化を狙うとそれに悩まされる印象です。4ステージ目辺りから特徴が出てきます。
何の説明もなしにゲーム画面に放り出されるなど不親切ではあるものの、システムは簡潔で、中盤までは解くだけなら難しいゲームではありません。一方、他のZachtronicsゲームに言えるように、最適化を目指すと奥が深いです。
[h1]どんなゲームなのか[/h1]
用意された12種類の分子のなかから自由に選択して設置し、それを操作して目的の分子を作成して出力するのが目的です。原子の周りにあるのは電子じゃなくて水素です。二重結合とかもありますが、原子の種類ごとに結合の腕の数が決まっていてつじつまが合うように自動で結合されます。
(例:Cの結合を切り離すにはHを与えてCH4をつくる / Oの結合を切り離すにはHを与えてH2Oをつくるなど)
分子を6個のエミッタ(外周のビットのようなもの)を使って操作するんですが、Opus Magnum と同じくタイムライン上にコマンドを配置してループで実行する形です。
使えるコマンドは、分子を奥に移動 / 分子を手前に移動 / エミッタを左に移動 / エミッタを右に移動 / 分子を左回転 / 分子を右回転 / 水素を1つ取り除く / 水素を1つ加える / 水素を1つ奥に飛ばす / 分子の出力 / 分子の削除、です。
(※設置画面でのエミッタの回転はE,Qキーでできます)
制約となるのは、エミッタが6個しかない、エミッタが外周にしか設置できない、実行中のエミッタの方向が固定されている、一番手前の分子しか操作できない、奥に飛ばした水素が予想外の原子にくっつく、水素を手前に飛ばす手段がない、などです。この制約がこのゲームを一筋縄ではいかないものにしています。
[h1]プレイ感[/h1]
最低ステップ数を競うのはいつもの Zachtronics ですが、いつものように最適化を試行錯誤するのが楽しいステージが用意されており、考え始めるとやはり熱いです。用意されている分子の種類が複数あるため、取れるアプローチが広めなのもよいところ。
チュートリアルは簡単な英文のみですが、Opus Magnum 既プレイヤーは直感的に理解できるでしょう。未プレイヤーなら先に [url=https://store.steampowered.com/app/558990/]Opus Magnum[/url] を体験したほうがいいかもしれません。
GIF生成機能を持っているので、SNS等で投稿して共有するのにも便利です。シンプルなグラフィックゆえ Opus Magnum より容量も圧倒的に軽いため、SteamでのGIFの共有にも向いています。
ランキングは、サイクル数 / モジュール数 / シンボル数、の3つです。モジュール数 = コマンドの設置数、シンボル数 = エミッタと分子の設置数のようです。モジュール数で競えるようになったのは嬉しいですね!Opus Magnum にも欲しかった!
初期画面を見るとステージ数は少なめに見えますが、しっかり歯ごたえがあります。(まだ触っていませんが)レベルエディタも搭載されたようで。コミュニティの投稿からピックアップした作品がこれからも追加されるようです。
[h1]気になる点[/h1]
1. 原子同士が複数同時に結合するとき優先順位があるんですが、それが明記されていません。終盤ステージではそこが肝になることがあるので、自分で探る必要があります。
2. 動作の順番として、1.水素の移動(結合は維持)、2.分子の移動回転、3.結合解除、4.分子の削除、5.分子の出力、となっているようなのですが、結合解除のタイミングが直感的ではありません。水素の移動と同時に結合が解除されるならもっとスムーズに解ける問題もあるのですが、これが開発の意図したものなのかは不明。
[h1]さいごに[/h1]
操作自体はシンプルですが、最適化を目指すと時間が溶けるいつもの感じです。アーリーアクセス中に18時間もプレイしました。Opus Magnum に熱を上げた人にはおすすめです。
[b]追記:[/b]
それなりに最適化にこだわったところ、先日プレイ19時間にして全ステージをクリアすることが出来ました。どうなったかって?EXTRA PUZZLESとして追加で34ステージが追加されました!わーい(白目)。あの...この EXTRA PUZZLES、サンプルセットが変わっていてクッソ難しいんですが...。










