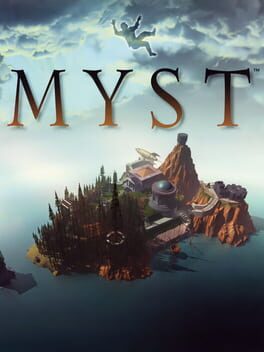The Hex
ビデオゲームの世界の忘れ去られた片隅にある、軋む古い居酒屋で、嵐が吹き荒れています。匿名の発信者は、殺人が計画されていると示唆しています。容疑者として有力なのは、ビデオ ゲーム ジャンルの主人公 6 人だけです...
みんなのThe Hexの評価・レビュー一覧
Ikagawa_Sii

2022年10月26日
私はネタバレが好きだ
ネタバレとは食品で言うなら成分表示のようなもので
触れたらアレルギーがあるものが入っていないか確認のために必要だ
このゲームのストーリーは始終メタ要素で構成されている
メタを扱ったゲームは難しくて 何が難しいかというとネタが被ると一気に陳腐化してしまう
スーパーマリオが楽しめるプレイヤーなら多分ソニックも楽しめるけど主軸がメタのゲームはそうはいかない
Steamで言うとこのゲームが扱っているものは The Beginner's Guide のような ゲーム制作に関する内容で
厳密にはストーリーそれ自体はあまり似通っていないのだけど
プレイしてそれが見え始めると ああ またその話か となってしまいがち
よって同種のメタを取り扱ったゲームを幾つかプレイした場合 最初に体験したゲームの評価が高くなる
この手のメタを未体験なら多分感動できるはず
ストーリー以外の実際のゲームプレイで言えば
色んなミニゲームの集まりで それぞれが長すぎず 難易度も適切で一気にクリアまで遊ばせる力のある作品になっている
お勧めします
Triple Okawari

2022年07月20日
Inscryptionが面白かったので購入。
正直な話、ゲーム内容に関してはそこまで面白いと思えるものではありませんでした。今となっては割とよくある感じのメタネタ主体のアドベンチャーゲームです。でも、もしこのゲームの購入を迷っているあなたが、Inscryptionが好きでその裏設定に興味があったり、イースターエッグ的な要素が好きなのであれば探究心と熱意次第で楽しめると思います。楽しむにはDaniel Mullins作品への探究心と熱意が必要です。一応サムズアップ。
Reversal!

2022年05月28日
[h1]事前情報なしに楽しみたい奇妙なゲーム[/h1]
あるホテルに「客の誰かが殺人を企てている」と電話がかかってきます。
宿泊客は全部で6人。いずれも癖のある見た目をしており、ただものでないことが伺えます。
犯人は一体誰なのだろうか…?
[h1]あらすじだけを見れば推理系ミステリーのようだが…[/h1]
このゲームはあの「Inscryption」の作者が作ったゲームです。
Inscryptionのことを知っている方であれば、このあらすじだけで収まるわけではないだろうと思われるでしょうし、実際その通りです。
宿泊客たちに関する情報が思わぬ形で開示されていくため非常に先が気になるつくりになっています。
気になった時がプレイ時な、とにかく情報を入れずプレイしたいタイプのゲームです。
変わったゲームをプレイしたいという方にオススメです。
IKSM_pasta[JP]

2022年05月06日
ついに日本語化。2022/05/10時点では、長文が低クオリティ翻訳なのが少し残念。
"ゲーム"という文化を愛する人にはたまらない一品。
個人的にはDaniel Mullins作品の中で一番好きなゲームです。
初見でプレイすることに意味がある作品だと思うので、少しでも気になるのであれば動画サイト等で調べたりするのは控えたほうがいいでしょう。
myacolyte

2022年02月13日
現代のゲーム文化をゲームキャラクターの視点から描いた怪作。
プレイヤーからすれば「あるある」で済む笑い話も、振り回される彼らにとっては悲劇以外の何者でもないことを端的に示していると言えるかも知れません。
第四の壁を越える話が好きならばやらない選択肢はないかと思います。
日本語訳されていませんが、DeepLやスマホのスキャン翻訳、PCOT等を使えば時間はかかるもののストーリーの全容を理解することは可能です。
願わくば、これをプレイすることで、私たちプレイヤーを楽しませてくれているゲームキャラクター達にもう少しの愛を持てる方が増えますように。
・追記
v1.13にて公式日本語ローカライズしました。
いちいち翻訳しながらプレイするのは面倒だという方も、この機会に是非です。
someone.told.me.it.was

2022年01月30日
Inscryptionは文句なしに最高だったんですが、こちらは微妙。
ゲーム内でミニゲームをクリアしながらストーリーの真実を探るという感じなんですが、ミニゲームは本格的なゲームの体をなしておらず、だるい作りで楽しめないわりに分量だけが多い。かといってストーリーの惹きつけもいまいち弱く、義務感だけでクリア。
オチも特にショッキングというわけでもなく、序盤から匂わせられているものがそのまま出てきた感じです。ストーリーをすべて知ってしまうと楽しめないかもしれませんが、配慮された事前情報を収集するくらいであればゲームプレイには全く影響を与えないでしょう。
satchmobgw

2020年07月13日
Great game, kept me hooked from beginning to end, and didn't overstay its welcome. The less you know going into it, the better. Just enjoy!
ぱすふぁ:Пазфа(○LIVE)

2020年03月15日
[h1] 現代の「ゲーム文化」に辟易している人にとっては痛快 [/h1]
Daniel Mullinsといえば、異色の名作Pony Islandの作者として知られている。つまり……
・単に攻略するだけならば単調な作業になることが多い
・ただし、ゲーム内部にはさまざまな裏要素がちりばめられている
という点で、本作The HexとPony Islandは似ているといえるであろう。
以下、全編(本作に限らず[spoiler]「地下深くまで」[/spoiler]探索し終わったという意味で)攻略を終えた結果の記述になるため、スポイラーを多分に含む。かなり長くなるため、これ以降個別のspoilerタグは省略する。
以下すべてスポイラー。攻略やストーリーについても説明の上で必要なため、上記「全編」を攻略したうえで参照されたい。
[spoiler]本作では「かつて人気を博したゲームの主人公たちが、吹き荒れる嵐の夜に、薄暗いバーに集まった」ところから始まる。突然、バーテンダーのもとに「いまからその中で殺人事件が起きる」という奇怪な電話がかかってくるところから本編で、まずは「Super Wiesel Kid」なる獣人の出番となる。
この「Super Wiesel Kid」だが、敢えて意訳するならば「任天堂の大人気配管工」に相当する。とはいえ、本作は「配管工ゲーム」を批判するためのものではなく、むしろ「ゲームというものに対して、プレイヤー(=我々)と本作(=The Hex)とゲーム文化が、どのような位置関係にあるか」を把握するために、わかりやすい例として提示されているだけだろう。
で、この「Super Wiesel Kid」シリーズの特徴として、最終ステージでは「Steamのレビュー」がステージの足場として登場する。当初は極めて好評だったものの、[b]好評ゆえに[/b]続編を出し続けた結果、同じようなゲームの繰り返しになるとつまらないとブー垂れ、また[b]最後の作品では期日に間に合わせるためなのかテストプレーもろくにできていないまま製品化、販売されたため、大量のバグについての低評価が多数つき[/b]結果として「Super Wiesel Kid」シリーズそして主人公のSuper Wieselは「地に落ちた」ことになる。
つまり、第1章では、レビュー・キュレーターありきのゲーム文化そのものを痛烈に批判している。ゲームとは、現代でこそ「収益をあげるためのメディア」の一部としてとらえられ、それ自体が間違っているとは言っていない(第1章のキャラが「任天堂の配管工」のオマージュであることから、これを否定しているというわけではない)だろう。しかし、そも、ゲームとは「娯楽の一端にある」メディアであり、すなわちホビーとは人それぞれに好き嫌いがあって当然で、万人受け(=レビュー高評価の[b]維持[/b]、一過性のものではなくあらゆる人々と世代からの高評価)するというのは既にこれ以上作れないのである、と主張しているように思える。つまり、こうしてレビューを書いていること自体が、この主張に対し謀反とも言えるのではないかとちょっと思わないでもない。
で、こうしていけば第6+1+1章まで全部説明できるわけだが、さすがに面倒なので「つまり、第n章では」だけまとめてしまおうと思う。
第2章:格闘ゲーム、今作の批判ネタは「コミュニティーが開発に口出しする」こと。人気キャラをほかのゲームにも登場させよう!というコンセプトで追加された主人公Bryce君(元料理人)がその格ゲーで当初弱すぎたので[b]「コミュニティーが」バフをよこせと言い続けた[/b]結果、その移植先の[b]格ゲーの元々の最強キャラよりも強くなってしまい、今度は「ナーフしろ」と[/b]……なんかこれ[b]某トム・クランシーの包囲網5v5の超次元FPSでよく見るやつやないか?[/b]ともかく「ゲームとは、開発陣が売れるために作るものになってしまっているが、元来は開発陣が楽しいと思うものを作るべきだろう」という主張を感じる。
第3章:RPGゲーム。批判ネタが複数含まれ、順序的にはまず「配信」という概念が入る。Twitch配信のコメント欄らしいものが右半分に表示されるシーンが何度かあり、主人公Chandrelleの選択次第では、例えばデバッグプレー用に用意されたショートカットを使用すると「チーター!」とか、あるいはマップ内のパズルやクイズを解くときには「***が答えだ」とか、まぁTwitch配信でありがちなスポイルが出てくる。何を批判しているんだ、と思う貴方は既にゲーム文化に毒されているかもしれない:ゲームとはそも、個人単位で楽しむものであり、スポイラーというものは(カタカナで書くとわかりにくいが)要するにネタバレのことで、楽しむことができたはずの要素がつまらなくなる。そして、現代のゲーム文化では[b]ゲーム配信という形式で、個人が個人のペースで楽しむことを否定している[/b]、何なら配信者とコミュニティーという「芸能人・アイドルが主導し、ファンが追従する」というのは[b]ゲームそのものを否定している[/b]と主張しているように思える。
第4章:ボードゲーム式ターン制RPG、本作での批判対象もまたコミュニティーについてだが、今回は「MOD文化」をかなり痛烈に批判している。第4章ではウェーストランドな土地で生き抜くRustなるジイチャンを操作することになるが、このゲームは開発陣によって「開発中止された」という経歴を持つ(ここまで前半)……はずだったが、そのデータをサルベージしたコミュニティーが「MODとして」その未完成ゲームの続きを勝手に作ったところから後半に入る。プレー中、MODあるあるのTrainer的なチートコード(攻撃力∞とかのアレだ)や、あるいはハードモード、それくらいならまだしも、主人公Rustが許せなかったのは、彼の弟の存在がこの「MOD」で「なかったことにされた」ことだった。つまり、[b]コミュニティーの勝手な開発の都合で、本来あるべきゲームの姿を修復不可能なレベルまで書き換えてしまうことが横行している[/b]ことを強烈に批判している。
第5章:トップビュー型シューティング、本作では第3章のサブキャラであるLazarusが主人公となり、剣ではなくライフル(と途中で見つければ両手マシンピストルやスナイパーライフル等々……)を持ち、スペースシップっぽいアレで敵の基地に降り立つところ……からスタートとなる。
今回は本作The Hexのクライマックス(の1回目)にあたり、第5章では本来展開される予定だったゲームを主人公たち自身が無視し、Gamework社なる建物へ侵入、敵をバッタバッタとなぎ倒し、責任者っぽいグラサン野郎を追い詰める。ここで第1章のSuper Wiesel Kidも登場し、この建物を爆破する。以降、第5章を終盤まで進めていくが、第3章でのプレー次第では、ここで「第3章の途中で登場したモブキャラ」に、「第3章のゲームが開発中止になったのはお前のせいだ」と言われる場合がある。ここらあたりで気づくのだが、本作The Hexの主人公たちはいずれも、このGameswork社が版権をもつゲームの主人公で、[b]さまざまなゲームを発売するにあたりキャラを使いまわしていた[/b]ことが類推できる。
それが確定するのが、第5章終盤で「モブキャラがたくさん閉じ込められている部屋」に到達したときだ。このモブキャラはみな、旧作(とくに第3章)に登場したが開発中止に伴い「凍結」された存在で(やんややんやと文句のシュプレヒコールを浴びながら)、最奥には(第3章開発当初に)ラスボスとなる予定だった女奇術師が凍結保存されていた……が、案の定そいつを解放してしまう。
……という紆余曲折があったが、ひとまずLazarus、目標であった「Artifact」が保管(というか、カットコンテンツが大量に箱に詰められて放置)されている倉庫に到着、そのArtifactに手を伸ばすと、例の奇術師に邪魔され、カットコンテンツ(ポケットなモンスターのボールの中身と戦わされ、完全防弾のフライパンを持たされてバトルグラウンヅに投入され、挙句この奇術師自身がキノコを食って巨大化)をプレーさせられ……とはいえどうにかArtifactを回収。
第6章:ゲームにおいて、操作キャラの姿が見えないジャンルが一つ存在する。いわゆる、FPP(一人称視点)である。第6章ではFPPのキャラを操作し「第5章までのキャラを作り上げたゲーム作家の生い立ち」を追体験し、[b]個人のゲーム作家が大企業に買収され、大企業がそのコンテンツで収益を上げる一方、ゲーム作家の意思や希望が蔑ろにされている[/b]ことを批判している。
第7章:第6章の最終版で隠しルート(いうほど隠していないが)を進むと「Super Wiesel Kidシリーズ」以前の作品の主人公である「バーテンダー」を操作、最終的にSuper Wiesel, Bryce, Chandrelle, Rust, Lazarus, FPPにバーテンダーの全員が揃い、第5章のArtifact「The Hex」の力で、彼らのバーThe Six Pintと、現実世界にいる彼らの生みの親が見ている画面をつなぎ、バーテンダーがその手で作者を窒息死させる……ところでエンディング(表)となる。
ただ、本作は他にも隠し要素が多数含まれている(それこそ、コミュニティー全体が探し回ってだいぶ時間をかけた果てにやっと見つけられるくらい、しかしDaniel Mullin曰く「Pony IslandにもThe Hexにも、まだ未発見の隠し要素がある」というのだが)ほか、解釈がほかにも可能な表現(意味がない、ということではなく、意図された表現が現実世界と関連性を示すものが多いということで)があり、公開からしばらくした本作だが繰り返しプレーしたくなる作品であることは間違いない。
とはいえ、本作は「ハデハデでドカドカなアクションは好きだが、頭をフル回転させるパズルゲームが苦手」という人には絶対におすすめできない。本作はドンドンパフパフドコドコギャーなゲームではないのだから。
[/spoiler]
[spoiler]
第8章:Steamで出ている釣りゲーム「Beneath the Surface」と、The Hexで達成できる実績については、別途自らの手で見つけ出すか、どうしても難しければSteamコミュニティーが一応エンディング(裏)を突き止めはしたので、コミュニティースレッドを確認してみてもよいだろう。だが、Daniel Mullin曰く、まだ隠し要素が存在するらしいが……。
[/spoiler]
sanuki

2019年07月13日
Pony Island作者の最新作。
6つのゲームの主人公が集まる宿、”The Six Pint Inn”が舞台。
「この中の誰かが殺人を起こす」という謎のメッセージを皮切りに、各主人公達のゲーム([spoiler]横スクロールアクション、格闘ゲーム、JRPG[/spoiler]など)を追体験しながら事件の謎を追っていくストーリーになっています。
まさにインディーズゲームならではといった作品で、インディーズゲームが好きな方にお勧めしたいゲームです。
また細かい寄り道要素や隠し要素、物語上の伏線も多く、ゲームを起動する度に新たな発見があり夢中になって遊んでしまいました。
一周プレイ時間6時間として紹介されており、英語が得意な方であればおよそその時間でクリアできると思います。英語が不得意な自分はもう少しかかりました。
ただし、前述の通り隠し要素の非常に多いゲームです。実績全解除、また様々な隠し要素を見てまわると少なくとも~20時間、もしくは~30時間程度にはなるのではないかと思います。
また、2019年7月現在日本語訳はサポートされていません。
文章主体のゲームなので量は多いですが一文一文は短めで、文章速度調整機能あり、バックログにも対応しています。
SOUMEN

2019年07月10日
宿に集まった、別々のゲームから集まって来た6人の主人公たち(横スクロールアクション、格闘ゲーム、RPG等・・・)の記憶を辿りながら、6人の中で殺人を計画しているのは誰なのかを探っていく、というようなストーリーです。
エンディングまでのプレイは6時間ほど、難易度が高い部分はさほどありませんでした。
「殺人の計画者を探す」という紹介から、推理要素が多く英語が難しいかなと思ったのですが、テキストが流れるスピードを調整できたり、ESCからログが見られるようになっていたりと親切な作りになっているため、クリアする上で困る場面はさほどありませんでした。難しい英語はほとんど出てきません。
インディーズゲームが好きな人ならツボに入るであろう演出が満載で、エンディングまで引き込まれっぱなしでした。
ここまでやるのか・・・というくらい無数にある隠し要素も、見つけるたび新しい驚きがあり、どんどんゲームのことが好きになっていくようなものでした。前作PONY ISLANDが好きだった人にも、強くおすすめできる作品です。
Haigyo

2019年06月30日
「誰かが殺人を計画している」
ゲームキャラクター達が集まる宿に匿名の電話が入る、という導入から始まるゲームです。
内容については多くの要素がネタバレになってしまうため、基本的に何も調べずに遊ぶことを推奨します。
[strike]日本語対応していないのである程度の英語力が必要になりますが、
メッセージの表示速度を調整できたり、メニュー画面で少し前までのログを辿れたりするので比較的読みやすい仕様になっています。(すべてではありませんが…)[/strike]
日本語対応しています!!!
※このゲームはPony Islandの作者であるDaniel Mullinsによるゲームです。
Maitake

2019年02月13日
決して明るいストーリーではないのですが、クリア後にはしっかりと満足感が残りました
特に終盤の展開はグイグイ引き込まれます
ただ説明文から想像するような殺人ミステリーや推理要素は期待しない方がいいです
難易度は普通にクリアする分には高くありませんが、例によって相当難解なシークレットがあります
全プレイヤーのうち3%にでも見てもらえればそれでいいみたいな感覚なんでしょうか
そこまで重要な内容というわけではないとはいえ、少しもったいない気がします
とまあこんな感じでネタバレを避けてレビューしようとすると大したことは書けないのでとにかくやってみてください
yoroshiku

2019年02月10日
怪作、PonyIslandの作者の最新作
前作をプレイした方は何となく分かるだろうが、このゲームもまたUndertaleやStanleyParableのようなメタフィクションやゲームならではのストーリーテリングがウリなので、ネタバレや不要な情報を一切頭に入れずにプレイするのがおすすめです
特にインディーゲームが好きな人向けかと思います
気になった方はすぐにこのレビューや他の情報を見るのをやめて何も言わずにポチるべきです
また現状日本語化は無いため、ゲームを進める分には義務教育レベルで何とかなりますがストーリーを理解するのには
それなりの英語力が必要なので悪しからず
belfaste

2018年10月19日
ダークメタパズル&アクション Pony Island で一躍名を馳せたダニエル・ミューリンズの新作。
今作もジャンル横断的なメタ演出がほとばしっている。
The Six Pint Inns という宿屋に集った六人のゲームキャラ+支配人。
ある夜、彼らのもとに謎めいたメッセージが舞い込む:
「このうちの誰かが殺人を起こす……」
一体誰が、なんの目的で人を殺すのか?
プレイヤーである我々は六人の客(それぞれ、横スクロールアクション、格闘ゲーム、ファンタジーRPG、終末SFSRPG、見下ろし型シューター、ウォーキングシミュレーターの主人公)にまつわる過去をひとつひとつひもほどいていく。
すべての記憶が開かれたとき、明かされる驚愕の真相、そして「殺人犯」とは……といったストーリー。
前回の題材は(ペニー)アーケードゲームだったが、
今作はご覧の通り我々が日常的にPCで遊んでいるようなゲーム、
それもインディーゲームと呼ばれるジャンルが題材となっている。
基本的には各ジャンルに沿ったミニゲームをこなしていくオムニバス的なスタイルだが、
そこは Pony Island の作者。実に凝ったメタ演出で我々を楽しませ、驚かせてくれる。
実際にどういった演出がなされるのかはプレイヤー自身の眼で確かめてほしい。
一例を紹介すると、
スーパーマリオ風の横スクロールアクションを遊んでいると、
最初はなんの変哲もない世界観だったのに途中から不思議な足場が登場する。
その足場はなんと今あなたが見ているような Steam のレビューコメントのようになっていて、
あなたが今現実につながっているフレンドたちがその横アクションスクロールをレビューしているのだ。
フレンドによる絶賛レビューの上を飛び跳ねながらゲームを攻略していくのはなんともへんてこな気持ちである。
この例からも見てとれるように、本作は単なる「ゲームに関するメタフィクション」ではなく、
「Steam というプラットフォームとその文化」に対する批評としても機能している。
あのキャラは弱すぎるから強化しろだの、あのキャラは強すぎるからナーフしろだの文句をつけるオンライン対戦ゲームのユーザーたち。ゲームをむちゃくちゃに荒らすMOD製作者たち。実況配信中にネタバレを配信者に教える観戦者たち。そして、そんな身勝手なユーザーにふりまわされて消耗しながらもゲームを作り続ける制作者たち。
本作は「犯人探し」でもあるが、一方でゲームというメディアにおける「被害者探し」を行うミステリでもある。
The Stanley Parable からはや五年(「外に出ろ」実績解除おめでとう)。
今日では、メタ的な演出が目玉となっているインディーゲームはさしてめずらしくない。
しかしメタ的な演出が効果的に使用され、しかもストーリーテリングそのものに貢献しているものとなると、ほんの一握りだろう。
メタをやるゲームでも終始そうした演出に徹するのは普通、あまり得策とはいえない。
最初こそプレイヤーも驚くだろうが、そのうちどんなびっくりエフェクトがきても感覚が麻痺してしまう。Undertale や Oneshot は「ここぞ!」という場面でメタるからこそクリティカルな体験を生み出せている作品だ。
特にゲーム制作者に眼を向けたものとなると、ゲームとしては決して失敗作ではないものの[spoiler]ICEY[/spoiler]の白々しいきまずさが思い出される。
本作はそうした高いハードルの数々を見事クリアしている。
エンディング自体はメタフィクションとして新鮮味こそないが、それまでプレイヤーが経験してきた道のりが感動を裏付けてくれるだろう。間違いなく、プレイに値する作品だ。
難易度はそんなに高くない。
パズルやアクションなど、ミニゲームのバリエーションに応じて試行錯誤が要求されるが、ミスしてもやり直しがきく上にそもそもパズル自体の難易度が高くないので詰まることなくエンディングまでたどり着けるだろう。
その点では Pony Island よりフレンドリーだといえる。
現状、英語のみで日本語化されているのは未プレイの人には懸念材料かもしれない。
だが、全編通して単語も構文もきわめてシンプルなので、中学英語程度の理解力でもわりとストレスなく進められるはずだ。
ただ一回に表示されるメッセージ量が少ないと言ってもクリック送りではなく自動送りなので、
読解速度に自信がなかったり、文意を隅々まで味わいたい場合はオプションから自動送りの速度を調節しよう。