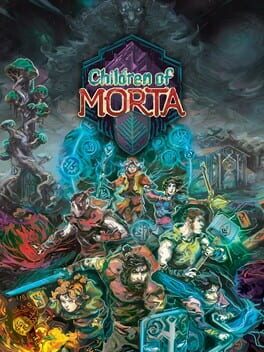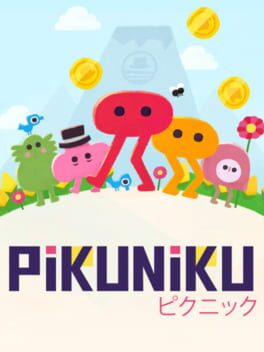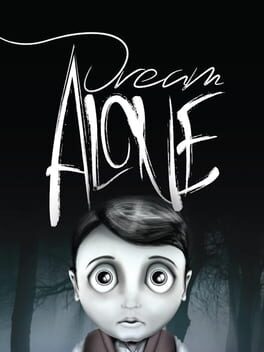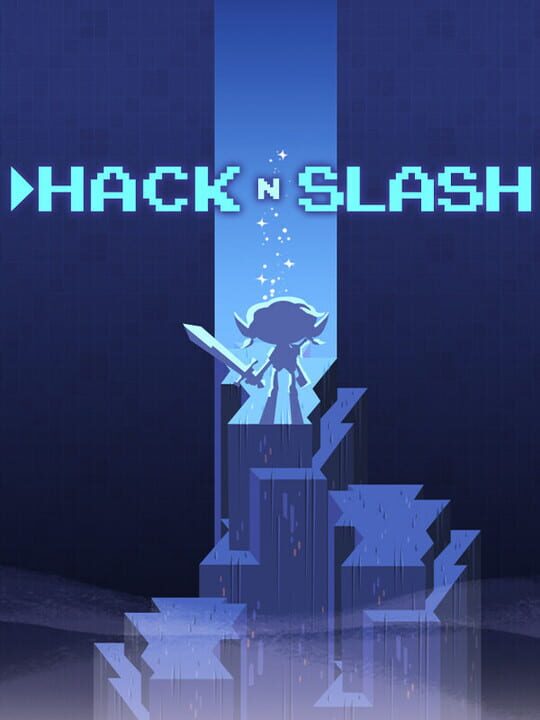






Hack n Slash
Hack ‘n’ Slash は、ハッキングに関するパズル アクション ゲームです。オブジェクトのプロパティを再プログラムし、グローバル変数をハイジャックし、クリーチャーの動作をハックし、さらにはゲームのコードを書き換えることもできます。勝つ唯一の方法は、ルールに従ってプレイしないことです!
みんなのHack n Slashの評価・レビュー一覧
yomenai

2015年02月02日
一応サムズアップはしているが、はっきり言ってしまうとゲームとしてはあまりほめられた物ではない
だがアイデアと特異性は評価できるし、以下に当てはまる人ならもしかしたら楽しめるかもしれないのでサムズアップしている
[list]
[*] Alice、Bob、Eveという名前でピンと来る人
[*] デバッガや出力関数の類を使用せずプログラムのコードを読んだだけでデバッグでき、それを楽しめる人
[*] 潜在的に上記の素質を持つ人
[*] ゲームはなんでも楽しめる人
[/list]
これらに当てはまっていなくても辛いだろうがクリアはできないこともない
でも途中で詰む可能性が高いし楽しめる可能性も低いと思う
始めの内は剣やブーメランでマップ内のオブジェクトやNPCのパラメータを変更して先に進んでいく
これだけだと分かり辛いだろうが、例えば敵NPCの攻撃性フラグを反転させて無害にしたりできる
一見某有名アクションゲームのパロディみたいな見た目だが、物事の状態を変更し問題を解決していく様はどちらかというとパズル寄りだ
このシステムを基にゲーム性を広げていったのならまあこういうゲームも有りだよねと思えたかもしれない
だがそれはAct3までの話(ちなみにこのゲームはAct2から始まる)
Act4であるアイテムを手に入れてからはアルゴリズムルームという所に入りプログラムのコードと対峙し改変していくことになる
コードは行番号 命令 文の順に書かれたBASIC言語風の独自言語になっている
正確にはlua言語のコードを独自言語風に置き換えた物だが
一応最初の2、3問は数行のコードの中から1ヶ所を変更するだけだし、妖精と会話すれば命令が何を意味しているかのヒントは出る
だけどそれまでオブジェクトのパラメータを弄ることしかしていなかったプレイヤーからしてみれば突然突き放されたように感じられても仕方がない
しかもコードはあっという間に複雑になる
当然各命令が何を意味しているか、文がどういう意味なのかは説明は無い
当たり前のように関数をオブジェクトとして扱っているのも酷い(lua言語では関数もオブジェクトなので)
また、コード内では文字で書かれた変数の他に色の付いたクリスタルも変数として使用されており、これがまた可読性を著しく下げている
大抵の場合ゲームという物は段階を踏んでできる事が増えていく
そしてそれらはいずれにしろ通常はそれ以前の要素から地続きである
残念ながらこのゲームではAct4以前と以降は地続きとは言えない
なぜならゲームの性質が変わってしまっているからだ
確かにやっていることはオブジェクトのパラメータの改変からコードのパラメータの改変に変わっただけではあるし、変数の操作はプログラムの一部に触れていると言える
しかしプレイヤーはそれらを通してプログラムを読む力を一切鍛えられてはいない
Act3までは直面した問題を解くゲームだがAct4からは問題を読むゲームなのだ
アルゴリズムルームも問題だ
アルゴリズムルームではプログラムのコードは台座とマシン、そしてマシンとマシンを繋ぐ線で構成される
台座はコードの文、あるいはその一部でマシンはコードの行を視覚化した物、線は処理の流れを示している
問題の1つはどのマシンも同じような形をしているのでどの命令を実行しているのか視覚的に分かり辛いことだ
各命令毎にマシンの形や色は極端に変えるべきだった
また、文法上繰り返し文は1行なため、マシンも1台で表される
つまり繰り返し文は視覚的には表現されないのでコードを読むしかない
実質的にアルゴリズムルームが視覚的に示せているのは条件分岐の接続先だけである
最大の問題はデータの内容が見えないことだ
プログラミングを抽象化しているゲームは他にもあるが、そういったゲームは大抵処理の流れと処理の結果が視覚的に分かるようになっている
処理の流れと処理の結果とは即ちデータの流れと変化であると言える
データが見えればコードが何をしているのかというのが視覚的に分かりやすくなる
データが見えると難易度が激減するので避けたかった気持ちは分かる
だがゲームとしては見えるようにするべきだった
開発者としては言葉で説明せずともアルゴリズムルームに入れば視覚的にプログラムを理解できると踏んだのかもしれないが、先に述べた諸々の理由によりかえって理解し辛い物になっている
コードを直接編集するのもアルゴリズムルーム内で書き換えるのもプレイヤーからしてみれば違いが感じられない
Act 3で画面内のオブジェクトの名前やアルゴリズムルーム内のコードを視覚化できるアイテムを手に入れるのだが、それで表示されるのはアルファベットで綴られた単語等ではなくアルファベットを置き換えた独自の記号で綴られた単語が表示される
これはとある暗号を解けば普通にアルファベットで表示されるようになるらしいのだが、問題はそれを解かなくても先に進めてしまうことだ
らしいというのは自分はそこを飛ばしてしまいその後苦労したからで、そのことは指摘されるまで気付かなかった
これを解いておかないと一部の問題やアルゴリズムルーム内の表記まで記号になるので大きなハンデになる
真っ当に導線を考えるなら強制的に解かなくてはいけない問題にするべきだった
アイテムにしても名前から効果を推測させる形式で基本的には説明が無い
また普通にプレイしている分には1回しか使われない、もしくは進め方によっては1回も使われないアイテムがあるのもどうかと思う
アイデアは本当に良いと思うのだが、とにかくゲームへの落とし込みがダメダメすぎる
プレイヤーの知識や想像力にゲーム性や導線を委ねすぎていてプレイヤーへの配慮といった物があまり感じられない
あらゆる物事を改変できることもウリなのだとは思うが、もっとプレイヤーを楽しませることを熟考するべきだった
これではアイデアだけ提示して「これ面白いでしょ」と言っているようなものだ
だけどここまでがっつりとプログラムのコードと対峙させられるゲームはなかなか無いと思うので覚悟できる人はやってみてもいいかもしれない
以下ネタバレ(Spoiler)
[spoiler]通常エンディングの後のAct6が存在する
別フォルダにSecretRoom.luaという暗号化されたファイルが存在する(復号化の鍵は自分も知らない、分かったら教えてほしい)[/spoiler]