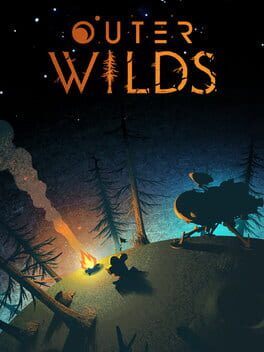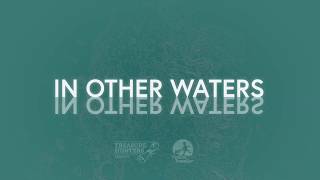





In Other Waters
人類の絶え間ない消費が星々を囲むまで拡大し、地球最後の生物生命体が毒に侵された惑星にしがみついている未来で、『In Other Waters』は、地球外生命体に遭遇した生物学者エラリー・ヴァスの物語を語ります。 定期的な太陽系外惑星の研究がうまくいかず、パートナーの野村美苗が異星人の海に消えてしまったとき、エラリーに残されたのは時代遅れの潜水服と、彼女を導く奇妙な AI だけだった。 彼らは一緒に野村を追跡し、不可能な生命を発見し、この異質な海を旅し、ターコイズブルーの波の下で永遠に失われるはずだった秘密を掘り起こします。
みんなのIn Other Watersの評価・レビュー一覧
2nd.mendota

2021年05月25日
テキストベースではありますがゲーム側主導と思っておくと良いでしょう。
読むのがゆっくり、途中でいろいろ考える、気分で一息つく、といったタイプの人には相性が良くないところがあります。
それと、なるべく流れに素直に乗って進むことを少しお勧めしておきます。
スタートと同時に反対方向へ走り出したり、敵が姫をさらって逃げたっていってんのに部屋に飛び込んで引き出しを片っ端から開けるような行動は控えた方がとまでは言わないものの、流れに合わせてというかタイミングを見て、の方がおそらく具合が良いかと思われます。
あ、あと人によってはマウスとコントローラを併用した方が楽かも。
takahashi

2021年05月21日
小説として出てたら良かったのにって思うくらいにはよく出来たSFでしたが、ゲームとしてはかなり弱いです。
この手の簡略化されたビジュアルのゲームは、音響に加えて多少のアクション性があると緊張感が高まる経験則がありますが、本作は音響面では良かったもののアクション要素は皆無でしたので、そこがゲームとして評価できない点になってしまいました。
BAD評価にはなってしまいましたが、まとまりとしては良く出来ていてローカライズも完璧だし非常に惜しい作品だと思います。
あくまで多くの人に面白いと声を大にして言える作品ではありませんが、自分は嫌いな作品ではありませんでした。
あとプレイ時間が30時間超えてますが、起動したまま忘れてただけなので、実際のところはメインストーリーだけなら5時間程度の尺に収まる作品です。
inohati

2021年05月05日
プレイする生物図鑑。
独特のシステムで最初戸惑ったけど慣れてくるとサクサク進められる。シンプル過ぎて好みは別れるかも知れないけど、映像を浮かべながら小説読む人はハマると思う。
少ない手がかりを元に大海を彷徨う不安感と、着実に、多すぎず増えていく情報量のバランスが良かった。
condor

2021年04月30日
[h1]海洋生物学者とともに未知の星の海を探索する[/h1]
100%クリアまで達成してのレビュー。
普段の生活では経験できないようなことを体験させてくれるのはゲームの魅力の一つだと思っている。本作は「海洋生物学者を手助けするAI」というかなり変わったシチュエーションが特徴。
[h2]システム面[/h2]
コントローラーにも対応しているものの、マウスのみで直感的に操作が可能(メニュー画面はEscで表示)。
本作はゲームオーバーの無いシステムとなっているため、迷ったり手持ちのアイテムが一時的に不足することはあっても、根気強く調査を続けていけばエンディングにはたどり着けるはず(それも8~10時間程度)。移動やソナーの反応など、(おそらく意図的に)反応が少しゆっくりに感じられるが、それがまた海中を調査している雰囲気作りに一役買っているとも言える。
[h2]シンプルかつ想像力を刺激するインターフェース[/h2]
テキスト量が多く、ゲーム画面も記号のようなシンプルなインターフェースであり、最初は戸惑うところもあるかもしれない。少しずつできることが増えていくようにデザインされているため、触りながら慣れていけるはず。
調査する海は穏やかなだけでなく、流れの速いところもあれば、有害なガスがわいているところもあり、ほとんど光の届かない深海もある。こういった情報は文字以外に色で表現され、酸素が不足してくる適度な緊張感もあり、良いアクセントになっていると感じられた。
[h2]謎を解き明かすストーリー[/h2]
深く触れるのは避けるが、先に来た科学者(ミナエ)の足跡を追っていくうちに色々な事実が明らかになり、驚くような事件も起きるストーリーは、興味深く進めることができた。
[h2]ローカライズ[/h2]
日本語対応は全く問題無し。特に、図鑑的に埋めていく調査記録は圧巻で、各種生物の生態についての考察や、いかにもそれっぽい(学術名的な)生物の名前など、センスを感じる素晴らしいローカライズが行われている。
[h2]総評[/h2]
およそストアページのトレーラーどおりのゲームで、この雰囲気にひかれる方にはおすすめ。
豊富なテキストから、未知の惑星の海の様子に想像力を働かせて楽しむことができると思う。
momoten

2021年04月25日
基本的にテキストベースで進行するゲームです。プレイヤーはオペレーター的ポジションからゲームに関わっていくのですが、ゲーム内のテキストが恐ろしいほど緻密で大量です。同じようなものをスキャンした時も、その時の状況に応じて微妙に内容が変わっており、かなり世界観が作りこまれているのがわかります。
テキストを通して世界を深くまで読み解くのが好きな方にはおすすめです。
クチナワ

2021年02月28日
ストーリークリア時点でのレビュー
プレイヤーは異星の海を探索する博士をサポートするAIとなって、進むべき場所を教えたり、資材の採取をしたり…
なんやらかんやらのお手伝いをするゲーム
翻訳の質はかなり良い
特徴的なのがプレイ画面で、基本的にプレイヤーはレーダー画面しか見ることができない。
しかし、博士の発言やリアルな環境音、特徴的な動き方をする生物達を表す点、そして博士のスケッチなどによって
ただの点しか存在しない平面からプレイヤーは世界を"観"ることができる。
レトロゲーム時代にはよくある話の一つである、ドット絵と説明書を見比べて世界を想像していたころを思い出した。
調査を進めれば進めるほど、このレーダー画面は美しく世界を映し出すだろう。
現在のグラフィックの美しさを追求する風潮に一石を投じる、意欲的な作品
t_hosoyama

2021年02月02日
システム面に関して最初は、チュートリアルも何も無いので何をしたら良いのか分らずでしたがプレーしている内に何となく理解出来るようになれば非常に面白いゲームだと思う。
このゲームはダイビングスーツ(AI)を着て深海を潜りスキャンをし探索をして行くゲームですが物体とかは形とかでは無く記号見たいな物で指示されます(私は記号の方が見やすく分かりやすいと思う)
後、コントローラにも対応していますがマウスでプレーするのがお勧めです(好みですが)
最初にも書きましたシステムを理解すると、こんなに面白いゲームは無いと思います。
私はお勧めしますね!
凹 / kubo

2021年01月08日
小説を読むのが好きな人。
とりわけ、映像を頭の中に思い浮かべながら読むタイプの人におすすめしたいゲームです。
わたしも昔、小説をたくさん読んでいました。
でもいつからか、仕事用の技術書くらいしか読まなくなっていました。
このゲームで、久々に「読む楽しさ」を思い出した心地です。
舞台は、美しい海に生命が育まれ始めつつある未知の惑星です。
でもその海の美しさを、プレイヤーは映像で見られるわけではありません。
プレイヤーは「AI」なので、浅瀬で陽を浴びてゆらめく海草も、きらきらと輝く胞子も、さっと飛来しては泳ぎ去っていく小さな動物も、すべて画面上の信号でしか表示されないのです。
それらすべては、この星に流れ着いて一緒に探索する生物学者のエラリーが、言葉を尽くして語ってくれます。
その言葉が詩的で美しい。ローカライズ担当の方ありがとう。
一文一文、情景を頭の中に映像で思い浮かべて、大事に読み進めました。
ゲーム性もきちんとしてました。
図鑑を埋めたり、物資と研究サンプルを天秤にかけながらやりくりするの、楽しかったです。
「ゲームという媒体を選んだ意味がちゃんとある」感がしてとてもよかった。
ひとつ残念なことがあるとすれば、「酸素ゲージがじわじわと減っていく」ゾーンがあって、そこではエラリーのコメントをゆっくり読んでいる暇がなかったことでしょうか。
あの「めちゃくちゃ切迫しているわけではないけどじんわり焦る」感じは、いかにも調査員って感じでゲームとして楽しめましたが、贅沢を言えば文章もじっくり読みたかった。
セールに乗じてサウンドトラックとセットで買いましたが、サントラも本当によい買い物でした。
ここ数年不眠がちで、youtubeなどで「よく眠れるBGM」などを探し歩いてきましたが、その中のどれより、このゲームのサントラがよく眠れます。
MikasaRxxX8

2021年01月01日
ストーリーをクリアしたのでレビューします。クリアまでにはゲーム内時間で4時間19分。
ゲームを一言で言えば海洋SFアドベンチャー。
ストーリーはストアページの記述を読んでもらえばわかると思います。
プレイヤーが行うことはスキャン、ルート設定、生物のサンプル回収で、すべてマウスによる操作です。アクション要素などはありませんがUIの説明がまったくないので最初は戸惑うと思います。一度使えばすぐ使いこなせるようになるのでこの点は問題ないと思います。
このゲームで特筆すべき点は、俯瞰視点にもかかわらず、架空の生態系を非常に高いリアリティをもって体感できる点だと思います。
スクリーンショットにもあるとおり、海中の構造は等高線つきの地図でしか把握できない上、あらゆる生物は黄色いアイコンで表現されています。一見リアリティもなにもないわけですが、それを補うのが膨大な量の「観察メモ」による描写です。
スキャンして次の行き先を選んだり、生物を発見したときにこのメモが表示され、エラリーの周囲がどういった状況なのかを知ることができます。
例:すべすべの石 大きなすべすべの石が砂に埋もれており、その先では茎たちの森の琥珀色のテラスを太陽が照らしている。
例:ショウグキ 音と胞子によって交信する、真菌生物。相互に結びついた生態系が礁の全域へと広がっている。
詳細なグラフィックがなくとも、こういった描写が架空の生態系の解像度を高めてくれます。
その生態系の作り込みにも驚かされます。プレイヤーはサンプルを回収して基地で解析することでより詳細にその生物について知ることができます。
スクリーンショット3枚目はその一部です。グンタイノハシケの観察記録がありますが、タブを切り替えれば生態、考察、そしてスケッチの記録を読むことが可能です。そしてこれは一部に過ぎません。自分の場合、ストーリーをクリアした時点でざっと19種の生物について記録がありました。
ストーリーはまさにSFで、設定とゲームプレイにうまく噛み合うものでした。あっさりといえばあっさりですが、このゲームで展開できる最高の物語だったと思います。
探索してドキュメントを読むのが好きなタイプの方には心からおすすめします。ボリュームは少なめなのでセール価格が妥当かなと思います。DLCにはデジタルアートブックとサントラがありますのでセットで買うのもいいですがアートブックはすべて英語なので注意が必要です。
この内容にも関わらず完璧に翻訳してくださったローカライザーには感謝したいです。ありがとうございました。
Masa Kei

2020年12月27日
まず一時間プレイして、最初の中継所の周辺を探索。操作方法や、標本の使い方はわかってきた。
UIとテキストのみだからか、うまく没入できる。深海に潜って調査研究してる気になれる。BGMも雰囲気出てる。トレイラーの曲を聞いたら分かってもらえると思う。酸素の残量を管理する必要はあるが、それほど厳しい制限ではなさそう。
ユーザータグに「実験的」とある通り、実験的で、美しいゲーム。
失踪したミナエ博士はどこへ行ったのか? 人類が初めて遭遇する地球外生命体という大発見をなぜ報告しなかったのか。この神秘の海で彼女は何を見たのか? 先が気になる。少しずつ進めて、またレビューに追記しようと思う。
Pocke

2020年12月09日
ミニマルなグラフィックにもかかわらず、海洋探査の緊張感やわくわく感が得られる不思議なゲーム。
自分で解き進めていくというよりは、海洋SF小説を追体験していくインタラクティブ小説のような作品だ。
生命に関するレポートやエラリーのコメントから環境を想像させるような作りで、レポート内容やスケッチから惑星の様子を推し測るプロセスがとても心地良い。
文章に関しては英語で読むには難解なため一度は投げ出したが、しっかりとした日本語ローカライズがされたおかげで改めて楽しくプレイできた。
作品の性質上、SF小説を楽しめる人にはおすすめしたいが、論文のような文体が苦手な人や、アトラクティブなゲームを期待する人にはあまりおすすめできない。
schappeee

2020年05月07日
In Other Watersをクリアしました。
だんだんと明らかになる地球の過去やGliese 667Ccのこと、生き物たちのこと…謎を紐解いていくごとに好奇心が刺激されるようなエキサイティングなゲームでした。
何より、AI目線でインターフェイスを通して未知の世界を観察するという体験がとてもユニークで面白かったです。
エレリーさんのnoteの文章を通して美しい情景を想像させられ、実際の風景を描写されるよりもとても感情を揺さぶられました。
100%クリアを目指してもう少しがんばります!
//
I have cleared In Other Waters.
It was an exciting game that piqued my curiosity as I solved the mysteries of Earth's past, the Gliese 667Cc, and the creatures.
More than anything else, the experience of observing the unknown world through the interface from an AI perspective was very unique and interesting.
I was made to imagine a beautiful scene through the writing of Ellery's note, and I was very moved by it more than the actual scene was described.
I'll try a little harder to get 100% clear!
tenko

2020年04月04日
レビュー時点では、未クリアです。
オススメにしていますが、製作者のこだわりが合う人にはオススメ、合わない人にはオススメしない程度の意味合いのつもりです。
決して万人向けのゲームではありません。
ゲームの概要
あなたは、AIとして、宇宙生物学者であるエルリー・ヴァスと異星の海中探索をする。
ヴァスは学者であるため、海中の生物のサンプルを採取するなどの調査も行い、生物の中には探索の手助けになるものもあったりする。
AIの視点であるため、特徴的なUIが使用されている。
DLCからも判るように、惑星の生物には詳細な設定があるようである。
良い点
・シンプルでユニークなUI
・他のゲームでは見られない雰囲気・ビジュアル
悪い点
・英語が多少読めることが必須
読むことになる文章の量が結構多い。
学者との会話はオートで文章が進むため、知らない単語を辞書で調べつつ・・みたいなことが難しい。(一応、メッセージログから再度見ることはできる。)
また、ゲーム中に採取した生物の図鑑があるのだが、文章量が多く、専門用語も多用されている。
ストーリーも、ビジュアル的な説明は少なく、文章で展開されるので、英語が読めないとよく分からない。
・ゲーム全体がシンプルすぎて、最低限度の説明しかされない
次にどこへ行けばいいのかがわかりづらい。マップで次の目的地が示されているのだが、移動時はマップを開くことができず、拠点に戻らないとマップを閲覧することができない。
UIや新しく入手したアイテムの説明も最小限のため、手探りで使い方を学ぶことになる。
結論
製作者のミニマルデザインへのこだわりが、良い点にも悪い点にも表れているように思います。悪い点に目をつぶれるほど、良い点が魅力的なら買うべきでしょう。
製作者のこだわりがプレイヤーに合うかどうかが全て、だと思います。
クリア後追記
全体としてみると、このゲームのジャンルはいわゆるウォーキングシュミレーターとか、ADVになると思います。
ただストーリー要素は相当にあっさりしています。
エルリーとの会話中に、返答を選択することがあるのですが、おそらくストーリーに影響はしないと思います。EDは一つだけでしょう。
個人的には、移動すること自体が面白いと感じました。
このゲームでの移動は、スキャン→目的地をクリック→スキャン終了→目的地に照準を合わせる→移動する、という作業が必要になります。この一連の作業で自機が一歩進みます。
文章にすると相当に面倒な移動方法ですが、この作業の繰り返しが何故かそこそこ面白いというか触っていて気持ちがいいという不思議なゲームでした。