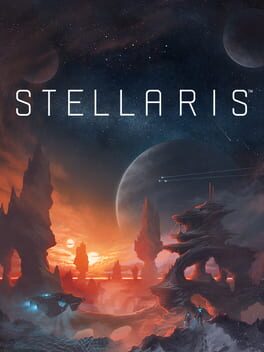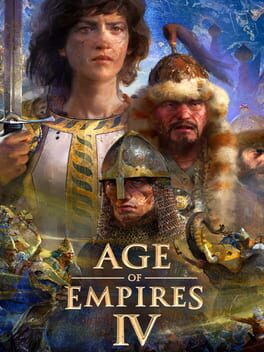Old World
Old World は、壮大な歴史的なターンベースの戦略ゲームです。古典的な時代を舞台にしたオールド ワールドでは、プレイヤーは帝国を築くだけでなく、その時代で最大の王朝を築くチャンスも得られます。
みんなのOld Worldの評価・レビュー一覧
Via

04月30日
このゲームのリードデザイナーがCivilization4の時マニュアルに書いたデザイナーズノートが名文で、それを読んで自分は世の中に「ゲームを分析的に作る」開発手法が存在することに気づいた記憶があります(余談)。
で、その頃の才能が翳るどころか、ますます洗練されたものが本作Old World、そんな印象です。
「あくまでゲームとして面白く遊びやすいシステム」と「実際の歴史や社会を作っているような絶妙な感覚」という、4Xの矛盾した魅力の実現においてOWは超傑作だと思うのですが、ちょっと伝わりづらかったり、大きく好みで分かれそうな部分もあります。熱心なファンもいるわりに、いまいち定番タイトル級になりきれないのもそこが一因なのかもしれません。
Civを主軸に人材システムや隣接ボーナス系の街づくりを備えた全体像にはさほど斬新さがなく、テーマとする期間も古代のみと、ありきたりや地味と受け取られても仕方ないところはあります。[b]ですが、[/b]命令ポイントやランダムイベントで支えられた具体的ゲームデザインと細部が極めて優れていて、そこにこそ自分はOWのユニーク性を感じます。
そんな細部を挙げていくとマニュアル書き写すのと変わらなくなるため、いくつかピックアップすると:
・命令のポイント制は何をするか取捨選択する戦略的な側面も当然ありますが、副産物としてマイクロマネジメント低減に大きく貢献してます。
要はポイントが尽きたら何もできないというのは、何もしなくてもいいのと同義なんですよね。顕著なのが、どんな大軍隊を作ろうと動かせるのは命令ポイントの範囲内なので、おのずと軍と戦争が妥当なサイズに収まる点。
また4Xプレイヤーにとって厄介な戦争中の内政にしても、そもそもできないんだから仕方ない、という割り切りが成立します。前線が1タイルの差で生きるか死ぬかしてるのに労働者や宮廷に回す命令ポイントなんかねえ!というわけです。逆に国内を整えたければ戦争をやめるべきで、そこに戦争と外交のメリハリが生じます。
第2の副産物として、窮屈なパラメータやペナルティをそぎ落とせています。上記の例で言うと軍サイズに対する累進コストや厭戦ペナルティがOWでは不要です。それでいて兵站や行政能力といった現実らしさも再現できている。
3つめに小さめのメリットを挙げると、命令というリソースで縛れてるため全体的にユニットの移動力が高く、ユニット配備に関するフラストレーションもだいぶ抑えられています。なんなら命令を大量消費して1つのユニットをとんでもない所まで動かすことも可能。さすがに通常を超えた移動はコストが倍増し、乱用は推奨されない作りですが。
・ランダムイベントはなかなか強烈で、Paradox作品比較だと体感2倍は影響が大きく、頻度も2倍ほど発生します(設定で頻度を下げたりオフにはできる)。私も初見はドン引きしましたが、遊んでみるとこれがしっかり役割を持っているんですよね。
たとえば「他家から身内を大臣に据えろと圧力をかけられる」イベントが発生し、現職大臣はかなり有能、しかし当の氏族は軍の主流派閥、みたいな状況だとします。氏族を満足させて戦争で頑張ってもらうのもいいですが、切った大臣が恨みで何かしでかすリスクが残ります。そもそも優秀な役職の出力するパラメータ上の恩恵は馬鹿になりません。
巧みに相互作用するシステム上で、この極端なイベントがある種のリソース配置を生成していると言えばよいでしょうか。別の表現をするなら「引いた初期立地にどういう都市を作ろうかワクワクする」4X序盤のあの感じを、ゲーム全体に拡大したらどうなる?という試みかもしれません。
ここらはロールプレイ的意味合いの大きいParadox作品のイベントとは方向が異なりますね(もちろんどちらが優れているという話ではなく)。
なにより史実や当時の習俗を絡めたイベントはシンプルに面白く、単純なトレードオフばかりにならないよう工夫されてます。プレイヤー指導者の属性もかなり影響し、こういう作品でフレーバーにとどまりがちな「善良」といった性格も獲得を狙う理由があるくらいになっています。
逆に前述のたとえで言うと、初期立地は安定して優秀であって欲しい、悪ければリセットも辞さない派の4Xプレイヤーにはやはり好みを外れるゲーム性かもしれません。
・入植候補地が決まっている(数タイル分の範囲はある)のもCiv系4Xでは思いきった仕様ですが、想像以上によく機能してます。なにしろ都市スパム問題と、息苦しくなりがちな拡張ペナルティを両方消せてます。[strike]そもそもCiv4に強い拡張ペナルティを導入したのが本作開発者なので、これはマッチポンプじゃないのかという気もしますが。[/strike]
固定とはいえマップ生成に合わせて候補地もランダムなので、単調には全然なっていません。むしろ人間は資源出力を最大化するように置くのでどうしても画一的になりがちですが、OWでは良い塩梅にそれっぽい都市配置になる感じがします。
また都市間を埋める国境線を拡大する手段も複数用意され、自国の領地同士なら最初から融通できるので、だいぶ好きにやれる作りですね
他にも、影響が分かりにくかったり把握が面倒になりがちな氏族、宗教、諜報活動などうまく割り切ってシステム化され、一方でプレイ中にドラマが見えてくる感じというか、ゲームだからと突拍子もない実装方法にはなっていません。
特に氏族(派閥)関係はめちゃくちゃ語りたいですが、レビューが倍の長さになりそうなので自粛。
戦闘は1タイル1軍事ユニットでユニット種別ごとに射程や特殊行動のある、いわゆる1uptのタクティカルコンバット。本作のAIはユニット特性や戦闘ルールをかなり使いこなし、同等国力では負けるリスクも無視できない程度には手強いです。つまり戦争がちゃんと面白い。
一方で戦争自体のシステムは単純で、宣戦を阻むのは停戦直後の5ターン猶予くらい。同盟は特定属性を持つ指導者のみ可能(このあたりも指導者の個性が飾りではなく、ゲームプレイを大幅に変化させてます)なため、連鎖宣戦はかなり起きにくくなっています。多分、古代なんだし気軽に殺り合えってメッセージです。
・現在はUI含めプログラム的な完成度も十分高く、終盤でも大して重くなりませんし、毎ターンオートセーブしているのにターン移行処理も早め。自分はしばらくオートセーブがデフォルトなことに気づきませんでした。
特筆すべき点として、あらゆるアクションをターン開始時まで無制限にアンドゥ・リドゥできます。イベントで重大な選択をしようが、斥候でFog of Warの中を見た後だろうが、戦闘行動だろうがお構いなしです。言うまでもなく非常にチート性の高い仕様ですが、そもそもセーブスカムをすれば同じことは可能だし、それよりプレイヤーの利便性を取ったということでしょう。
実際、命令ポイントやCiv6系の複雑な建設条件の管理は、(特に慣れないうちは)アンドゥなしだとちょっとやってられないところはあります。なおランダム関係はターン毎に確定しているので、乱数引き直しをやる理由はありません。
もう1つゲームプレイ以外で書いておきたいのは曲の良さ。こういう作品のBGMはクラシックやアンビエント系でまとまりがちですが、格好良く耳に残るものが多いですね。
・と、本当は色々な方にお薦めと言いたい作品ですが、それを阻む要素も幾つかあります。
- ゲーム内辞典が微妙です。チュートリアルは充実してますし、データも網羅されているのですが、もう一歩踏み込んだ説明がざっくりすぎたり記述抜けがあったり、全体的に完成度が極まってる中ここだけ謎のWIP感が漂います。
さらに日本語だとシステム用語まわりの翻訳が粗めで初期ハードルを上げてます(まず最初に都市を作る時点で、これは各氏族の私領扱いになるのですが、Manorを邸宅と訳してるので「なんで家建てるんだ…?」と首をひねる羽目に)。イベントや解説文などの長文はほとんどが自然で良い訳だったりするので、一度覚えてしまえば問題はないのですが。
- ゲームのコンセプト上どうしようもない話ですが、プレイ中は息つく暇もないほど面白い一方、終わり方がにょろっとしてるといいますか…Civが古代から現代まで描いているのは飾りではないんだなぁという印象。もちろん都市は立派になり国内は様々な人材で溢れ、OWなりの進歩した感はありますが、とはいえ航空機や核といったパラダイムシフトが起こるわけではないですしね。
1ターン1年設定だと決着ターン数はだいたい100強なので1ゲームも短めですが、これは人によっては長所でしょうか。
・最後に軽くDLCに触れておきます。4Xに欲しい要素は本体で揃っているため、おおむねDLCはその深掘りといった形。たとえば神々の怒りはいわゆる災害DLCですが、これも元からあるランダムイベント制のバリアントといった趣きで、特に厄介だったり難易度を上げるものというわけではないです。演出がとても雰囲気あるので、自分は1、2回慣らしプレイで切った以外はオンにしています。
またOWでは指導者が属性の組み合わせだけではなく、それぞれ独自の仕組みで表現されているので(エジプトのクフは、死後もピラミッドのある都市に建設バフを残したり)文明追加DLCのプレイバリューは高いです。
玉座の影はやや例外的に、タイトルだと諜報関係に見えますが「プレイヤー指導者に伍する国内有力者」が生まれるようになる新要素DLCで、これは単に権力が欲しい貴族であったり、英雄であったりします。烹ないといけない走狗、グリフィスに対するガッツみたいなもので、頼り甲斐のある部下であり友(プレイヤーにとっては優秀なユニット)が、しかしいずれ刃をこちらに向けてくるかも…とかエモ展開もあり得ます。
ただ内戦が起きやすくなるため、難易度というか情報量は相応に増える感じでしょうか。
再三になりますが、命令ポイント制のためDLCで「やれること」が増えても、それはプレイの幅であって総操作量はさほど変化しないんですよね(厳密には追加された効果などで命令ポイント上限が少し増えやすくなってるでしょうが)。改めてよく出来たシステムです。
ともあれどのDLCも導入価値は十分以上にあると思います。
Yoshitakamui

01月01日
Civilizasion風に仕上げられた戦略シミュレーションものです。古代文明の指導者として歴史上消えていった古代文明と覇権争いを行います。登場する臣下は様々でランダム生成もされるようです。与えられる役割によって活躍したり時には自国の足を引っ張ったりします。資源管理を行い、都市を開発し、技術を発展させ、法律を敷き、国家的建造物を完成させ、政略結婚を行い、競合する他国に挑みます。現代戦が含まれてしまうCivilizasionは好みではなかったのですが歴史的な文明の指導者が登場し様々なイベントを体験できるこちらは楽しむことができました。ゲーム進行はリアルタイムでなく、プレイヤーが要領よくゲームを進めるなら長時間のプレイ時間を持たずプレイできるかもしれません。
curoe_male

2024年10月10日
[h3] お勧めにしたいけど、現状だと攻略サイトやらで色々調べているうちに飽きるかもしれない。[/h3]
一応、最高難易度でクリアー済。
[h3] 感想[/h3]
① レビューで勧められていた為、「Old World コンプリート・エディション」で購入したのですが、そこまでしなくても良かったかなーという感じでした。
もしかしたら個別シナリオまでやれば違うのかもしれないですが、4X系ってこの手のシナリオものと相性はあまりよくないと思うんだよね・・・。どうにもやる気がおきませんでした。
② ヘルプのポップアップが微妙にわかりにくい。
これは日本語訳がおかしいという話ではなく、説明としてそもそもわかりにくかったりします。 ただしチュートリアルは割かしちゃんとしていて、このゲームをやる最低限度のチューターになってくれる。 ただし「プレイを通して学ぶシリーズ」の3と4はやらなくて良いです。通常プレイで気づける事なので時間の無駄になります。
③ 日本語訳が一部おかしくて、例えば
野望「探索法律を開始する」は正しくは「法律”探索”を制定する」。
野望「世界宗教で神話個の神学を確立する」も同様。これも法律関係。
野望「フォーラムを6つ管理せよ」は「6つの都市にフォーラムを作れ」という意味。
他にも、
「[全ての都市]+40%河川上の建設物から」
「[全ての都市]隣接する建設物クラスに-20%コスト」
とあるのが、実際には
「[全ての都市]+40%河川上の農業収益率」
「[全ての都市]同じ改善施設を隣接して建設する際-20%コスト」
が正しかったりします。
④ 都市を滅ぼすことができるのに、都市候補地を新たにできないのは納得できない。
シヴィライゼーションで慣れてる人が一番不満に思うのはこれだろう。
正直、これは「入植」が取れた時点で、莫大なコストはかかっても新たに都市建設できるようにすべきだと感じた。
⑤ 説明が無くて、困惑したこと。
改善施設は国境に接した場所では建てれない。
都市設立する2マス以内に敵のユニットや敵の建物があると建立できない。
製材所は低木では建てられない。
都市征服しても鎮圧中は中立地帯にならない。
評議員とは「王」「後継者」「大臣」「大使」「スパイ長官」の5人の事である。
これは説明がないんだよなぁ。
またチュートリアルでは説明があったが、ポップアップ・ヘルプで説明で不十分なものだと、海などを渡る際に「船を置き、いかりを下し、その次のターンから渡ることができる」のですが、そうした説明ではない為、わかりにくい。
[h3] ・その他[/h3]
① 設定オプションについて
文字が小さすぎる→アクセシビリティにある「HUDスケール」で対応できます。
ちなみに「-」がオンで「〇」がオフです。
② 文明の特性以上に指導者の特性が重要だったりする。
たとえばローマのアグリッピナは最初からスパイ長官を任命できる。
ペルシャのダレイオス。[全ての都市]都市の統治者を有効化。これはチートだと思う。
③ 氏族(家臣)の特性はもっと重要かもしれない。
なにせ、都市を設立したら、かならず氏族に与えないといけないからだ(これもどうなんかなぁって思う)。
氏族の属性はいろいろなメリットが付属してくるのだが、おすすめは「地主」。地方専門家のコストが-50%、植民が獲得しないうちから「土地タイルをゴールドで買収できちゃう」から。ただし、土地タイルを買収しまってると土地が高騰しまくるので多用は余りできないのだが・・・。
④ 宮廷大臣は氏族からよりも、技術に付随する無料の大臣を狙った方がよい。
それも子供が結婚適齢期の時に獲得すると、年齢しだいですがお嫁さんもしくはお婿さんの対象にできます。これは氏族からの紐付きでないので氏族絡みの悪いイベントに巻き込まれにくくなります。
⑤ 結婚は17歳ぐらいだったかな、それぐらいでできるようになる。
後継者をクリックすると結婚イベントの項目があるのですぐさま行おう。 なぜなら、このゲーム、ターン/年のため、あっという間に結婚適齢期をすぎてしまうからだ。
⑥ ターンは年ごとではなく、季節ごとが望ましい。
子供を作れる期間などがあるようなので、結婚適齢期や出産適齢期には神経をつかうため。 それに季節ごとにすると、寿命を現実的にしても自然になります。
⑦ 戦闘ユニットの強化する建造物
・巨像:新規のユニット:レベル+1
・霊廟:新規ユニットに「守衛1」
・ネイトの神殿:新規の遠隔ユニット:レベル+1
・ミスラの神殿:新規の遠隔ユニット:レベル+1
・ハルキの神殿:新規の遠隔ユニット:レベル+1
このゲーム、都市をどんどん作れるシヴィと違って、まじで1ターンや1ユニットが重い上、ユニットの強化コストも重い。ので、これらの施設はまじで強力なものになります。
⑧ 実績「ハードコア」の条件
「難易度・偉大なるもの」「イベント頻度・高」「寿命・現実的」「セーブをロック」「冷徹なAI」「取り消しの禁止」をしたうえで「すべての国家(8か国)」を相手に勝利する。
denmao

2024年08月26日
4Xジャンルに対する問題意識と示唆に富んだ端正な4Xでありながら、Crusader Kings的なキャラクター要素によって生じる歴史ドラマ(往々にしてろくでもない展開になりがちなんだけど、それがまた古代オリエントらしくて実に良い)が楽しいゲーム。
CivilizationやHumankindといった他の歴史系4Xが太古から未来に至る人類文明全体を俯瞰する壮大なスケール感を持つ一方、Old Worldは大胆不敵にも「古代オリエントおよび地中海世界」を舞台に1ターン1年という極めて限定的なスケールで展開される。この違いによって従前の歴史系4Xでは手が回らなかった歴史の重要な側面、すなわち人間ドラマの表現が可能になったというのがOld Worldの最大の特色。たとえば王位継承問題から内戦に突入して国がぐちゃぐちゃになるというのは、明確な勝利条件に向かって突き進む4Xゲームにおいては明らかに遠回りでありバッドイベントでしかないんだけど、これがふしぎと満足感がある。「ああ、それもまた歴史の1ページだな」というか。氏族が結託して王位簒奪が起こったりすると、ほーそうきたか(腕組み大沢たかお王騎)みたいな感じになる。歴史の奔流に身を委ねる快感とでも言いますか、CK、Rimworld、あるいはシムズなんかに見られるようなランダム性(RNGesus)によって紡がれる気まぐれで予測不能なストーリーテリングに一脈通ずる楽しさがあるので、そういうのが好きな人には特におすすめ。
数千年にもわたる人類の営みが高度に抽象化されるがゆえに必然的にある種ボードゲーム的な性格を帯びるCivに対し、Old WorldはCivとは逆のアプローチを採ることによってより歴史ゲームらしくなっていて、良くも悪くもCivの影響下に囚われがちな歴史系4Xにあって、Civの重力を振り切って独自の新境地を切り拓くことに成功している。
「より没入感の高い歴史ゲームとしてのCiv」を探してる人にとってはここがあなたのアルファケンタウリかもしれない。
minomontaurus

2024年07月28日
個人的には面白いし好きなんだけど、最近は和訳されてない部分が多くなってきてる気がしてる。気のせいだろうか?
日本語じゃないとわからないので徐々に遊ぶ時間が減ってきている。
Kenji Kndk (JP)

2024年07月23日
2024年のサマーセールに当時の『完全版』を購入し、ゲームの一回クリアした感想です。
一言で言うと、パラドゲーの「クルセイダーキングズ3」(以下CK3)のシステムを簡略化し、選べる文明とその指導者・使える技術とその兵種は全部古代(3-7世紀)に制限し、ゲームの進行をシヴィライゼーションにした作品です。
4Xヘックスの部分は言うほど他の4X作品との差がなく、UIが違うものの、根本のシステムはシヴィライゼーションにすごく似てるため、他の4X作品をやったことのある人ならすぐ慣れると思います。
他の4X作品との区別として、まずはCK3ようなイベントシステムを採用しており、イベントによってある程度のランダム要素が追加されてます。
ただ、イベントからの影響はCK3の程ではなく、イベントのせいでゲームオーバーになることはあまりないと思います。
もちろん、こういうランダム要素を嫌がる人もいるけど、ゲームが始まる前の設定でオフできるので、無理矢理にイベントをやらせることはありません。
戦闘ユニットは3ティアしかないので、種類は多くないけど、シヴィライゼーションに比べて戦闘バランスがいいから、まずティア差だけで一方的に虐殺されることがありません。
ただ、このゲームはいろんな意味で複雑化したシヴィライゼーションとも言えるので、4X経験者だとしてもこのゲーム特有な部分に慣れるまでなかなか苦労すると思います。
たとえば資源の種類が結構多く、そこら辺の管理はどっちかっていうとRTSゲームのような感じもするので、戦闘ユニットの生産と資源の収集の関係性に気付くまで、特定な資源が足りないという状況になりやすい。
特に、このゲームには命令という資源があり、ユニットの移動・街の開発・軍隊の強化・一部のイベントの選択などはこの命令を消費します。
そのため、とりあえず毎ターンもすべてのユニットを指示できる他の4Xとは違い、こっちは終盤になるほど命令が足りなくなるので、自分の行動をよく考えないといけないです。
クルセイダーキングズ3の要素を取り込んだため、族譜や家臣などのシステムもあります。
自国の氏族の友好度や外交・宗教などの行動は全部家臣で行うため、各役職の仕事を理解するまで割と混乱します。
その中に、有望株と言われる家臣の処理は一番面倒で、例え良好の関係を築いても反乱する時は反乱するし、反乱しなくても大宰相の座を求められ、場合によってすべての町の生産が変更できなくなるになるため、4X系にとって割とシャレにならない悪影響が出ます。
その他、部隊の大陸間移動の方法もやや特殊で、たまになぜか向こうの陸地マスに移動できないと一瞬だけわからなくなる時もあります。
あとは宗教関連の部分はチュートリアルにも教わってないから、そこはガチで自力で理解するしかないのです。
まとめていうと、「シヴィライゼーションをやりたいけど、中世以降の技術はいらねぇ…」と思ってる人向けの作品です。
シヴィライゼーションのような4Xゲームだけじゃなく、実はイベントを特化したロールプレイでも可能で、4X作品として結構多様なゲームプレイができます。
そのため、既存の指導者だけじゃなく、能力をランダムにした無名の指導者を選択することもできるし、その名前も変更できます。
ロールプレイ好きな人にとっては割とありがたい機能です。
他のレビューではゲームの終盤になると処理落ちやAI長考がひどいとよく言われるけど、実際これは4X系のよくある問題で、このゲームだけではありません。
それに自分のローエンドPCだとしても、確かにゲームをクリアする直前ではAIのターンがやや長くなり、カメラが遠くにいるAIのユニットに移動する際はスムーズではなかったが、それでも妥協できる範囲だと思うので、自分の環境だと言うほどの問題ではありませんでした。
ただ、このゲームは別に安いというわけではなく、群を抜いた作品でもないから、買うならセールで、って感じです。
マイマイやすりん

2024年02月04日
地味すぎてつまらない。
とにかくやたらと文字を読まされてばかりで面倒。
チュートリアルで飽きた。
戦闘シーンぐらいアップにして派手にしてくれればいいのに、マップ上でチョロっと動いて終わりなので面白みが全くない。
イベントが多いと言っても、すべてが文字で読ませるだけなので、ただただ退屈なゲーム。
なんというか、数字と文字を見てるだけのゲームって感じ。
ゲームと言うより、つまらないゲームブックを読んでる感覚になる。
音楽も宗教的すぎて暗い雰囲気のものが多いので気が滅入る。
あまり馴染みのない国の歴史観だからかもしれないので、ゲームに登場する国が好きな人とかでないとあまり楽しめないと思う。
日本人にはちょっと難しいかなぁ?
ehimamikan124

2024年01月05日
説明が足りなさすぎるのが本当にストレス
たとえばゲーム中の説明で、「この法律を採用すると土地を金で買える」とか「宗教を国教にするとこういう効果がある」とか書いてある。しかし、ゲーム的にどのような操作をすれば土地を金で買う行為ができるのか、どういう操作で国教を制定することができるのか、説明を見てもどこにも書いていない。
DönerBey

2023年10月12日
火薬が本格的に戦術に取り入れられる前の中世初期までの時代をプレイするストラテジーゲームは本作が初めてでしたが、王位を継承して遊ぶスタイルもスーファミ時代のロマサガ2以来だったため、新鮮であり、かつプレイ対象の国も個性的で難易度も高くカスタマイズも可能なため、リプレイ度も高く、全体的に満足しています。
ただし、前述した革新的な技術は出現しないため、ゲーム終盤になると研究できる技術が無くなってしまい、ライバルとの技術の差も次第に無くなっていってしまうので、ある意味この部分はいただけなかったです。プレイヤー側が劣勢の場合は、いいとは思いますが、現実性に欠けるかなと。しかしながら、総合的にシヴィライゼーションを初めてプレイした時の感動を味わうことができました。今後のアップデートにも期待します。
akipi_

2023年07月20日
個人的には良くも悪くもなんか眠くなるゲーム。
指導者、宮廷メンバーを頑張って育てたと思ったら病死や引退やイベントなんやかんやで一進一退を繰り返し、気付いたら夜が明けてる感じ。宮廷メンバーが減ると都市の監督者が変わって出力が落ちたり、指令書が減少して泥沼になりがち。特に指導者交代は親族がごっそりメンバーから外れたりするので悩みどころ。
逆に宮廷メンバーが増えるイベントはとても有難い。宗教や結婚等も色々考える事になる。
都市出力が少しづつしか伸びないし、特化した戦術で一気に攻めるストラテジー的な面白さはあまり期待しないほうが良いかも。国の勃興をのんびり見守りながら指導者と都市の育成をゆるりと進めるのが一番いい楽しみ方かなと思います。
pouDX

2023年03月23日
最初に結論を述べるとこのゲームは人を選ぶストラテジーであるため購入に際しては良くゲーム性を調べた方が良い。
個人的な評価としては85/100点といったところ
詳細設定によりCivilaizationの様に硬派なストラテジーとして遊ぶことも出来るが、このゲーム特有の氏族や勢力とのイベントの破天荒さを楽しむ方が満足度が高いだろう。
逆に言ってしまえば、そういったイベントによるランダム性を楽しむ遊びをしたくない、イベントに計画を崩されたくない諸氏にとってはそれらイベントを排したゲームは味気ない上に目新しいシステムも無い、ユニットや改善も充実しておらず、わざわざこのゲームを購入する意味は薄いと思われる。
暫くプレイをするとこのゲームに置いて真の敵はライバル勢力ではなく、自勢力の派閥関係であることが理解できるだろう。
悪関係にあるキャラクターが容赦なくプレイヤーの指導者キャラクターを排除し、足を引っ張られて自国の生産力がガタオチする事なんて茶飯事だ。
よってこれを如何にして回避するかが肝なので自勢力の機嫌を常に注意しつ他のライバル勢力から攻撃されないように上手く関係を維持しながら自国の強化を図るというストラテジーというよりはマネジメント側面の方に比重が置かれている。
*以下追記*
最新のDLCまで含めた評価をすると95/100点の内容に大きく変貌する。このゲームをプレイするなら是非DLCを全て導入しよう。
DLCによって追加される内容は以下の通り
・プレイアブル文明の追加や各文明に様々な特徴を持った指導者が追加され文明毎に戦略の幅が広くなる
・宗教・大宰相等の恩恵や弊害により、ある程度のランダム性で戦略を崩されながらも決して単調なデメリットを受ける訳ではなく飽きさせない素晴らしいゲーム体験
・強力で戦略的価値が高い遺産の追加、歴史上の著名な将軍や宗教家等のキャラクターのイベントや廷臣化
シミュレーションゲームとしては独特の癖と不条理なストレスが存在する一方で、度々変わる状況下でターン毎に限られた命令権の消費先を常に考え続けながらプレイするのはこのゲームならではの面白さに繋がっている
mino

2023年02月24日
2024年の5月になり、まとまった時間があり、再度集中的にプレイしました。
日本語(あるいは日本)では、詳しいゲームの進め方などの記事が極端に少ないため、バビロニアで200ターンの時間勝利をした方法について、核心の部分を避けつつ、アウトラインを記述します。
まず、ゲーム開始の時点ですが、より多くの都市拠点を抑えることが必要です。完成度が高いゲームだけに、拠点の数=勢力の力、という当たり前の原則が当てはまります。このゲームの特徴は、ターン数が進み、2~3勢力に収斂すると、そこから自分の勢力が仕掛けた形での完全制覇が非常に難しいことにあると考えていますので、その分初動が大切でしょう。
当初はマップの“霧”がデフォルトですが、自勢力が相対的に多くの拠点を抑えるために、霧を解除するのも選択肢です。
次に、研究を如何に他勢力に先駆けて最速で進めるかが重要です。これは、幾つかの兵器を戦場に投入されると、どうしても不利になるため、それを防ぐためには、自分たちが先行するしかありません。もちろん宗教面も進める必要があるのですが、キーポイントとなっている兵器を最初に取得することは必須の様子です。
そして、やはり“ゲームの仕組み”を知ることが大切です。順調にターゲットを定めた国に侵攻しても、突如異常なペースで高いレベルの兵器を量産される、という事象が必ず発生します。上段の研究の話と一緒で、これを上回るには結局、自分もこの操作を行う必要があるため、どうしたら、高度な兵器を異常な速度で生産できるのか、を習得する必要があります。
ちょうど(時間勝利のターン数である)200ターン位で2か国、3か国の「鼎立」状態が発生すると思いますが、ここから相手を倒す方法があるのか、否か、また時間ができたときに挑戦したいと思いますが、全部の相手国を倒して勝利を得るには、発想を転換して、ここまで記述した中の「ある状況」を逆手に利用するのが良いと思いますが、私自身はその方法が好きでないので、試していません。
日本でもう少しこのゲームに関する情報が出てくるのを祈っています。
(以前のレビュー)
地中海・北アフリカ・アラビア半島の紀元前200年から500年ぐらいを題材にしたシミュレーションゲーム。他のゲームとの比較を基に感想を書いている方が大半ですが、類似?(兄弟?)ゲームせずに始めました。
マップ上の敵を全て征服するのみでなく、設定ターン数内での勝利やゲーム内でポイントを蓄積することにより勝利をする(デフォルト設定はこちら)ことができるようになっており、いわゆる勝利条件も複数あります。ほかのレビューでは、内政で勝利した、戦争メイン、などまちまちのレビューがあるのはそのためで、ゲーム開始前に自分にあった「詳細設定」をすることが、楽しく、何度もプレイする一つの条件だと思います(デフォルトでも少し難しめ)。
デフォルト設定だと、ゲーム開始時にマップ中央である場合が多く、周囲を敵で囲まれることが多いため、難度が増加します。私はマップ「も」探して、マップ端を確保できるようなマップをプレイし、大分進むようになりました。また、デフォルトのターン数200(超過してもゲーム続行可能、ただし勝利判定なし)では、すべての敵を征服するのはかなり難しく、特有の「勝利条件」での勝利を目指すことになります。
氏族と技術ツリーも良くできていると思います。跡取りいないことによるゲーム続行不可能はほとんどない様子ですが、代替わりし続けますので、必要な人に必要な能力が備わっておらず、それがゲームの進捗を阻むことはあります。例えば、同盟を結ぶためには、王自身が外交官のキャラクターを持つ必要がありますが、同盟したいときに自分の操作する王に外交官の素質が無いことがあると、停滞・ゲームオーバーになるなど、ルールを良く理解してプレイする必要があります。また技術ツリーも取得の順番が非常に大事であり、選んだ国家に特有の兵器などを早く開発しないと軍事力で負けるなど、こちらもそれなりの難しさ、ゲームルール理解が求められます。
イベントのランダムさは、「生きるっていろいろ思いがけないことが起こるよね」と思えれば、真実に近いと思えますし、「ゲームだからランダムイベントは不要」と思えば(よく探すと)詳細設定で解除でき、理論(論理)上のゲームが展開できると説明文にも書いてあります。
ゲームの数多い設定や条件を理解し、なおかつ本家のwikiなどを参照しながら当時の国家の特色を理解できると非常に興味深く遊べると思います。
日本人的感覚で言うと多分、三国志であれば、歴史物語として親しんだことがあり、ゲームとしても歴史的・登場人物の背景があらかじめわかって苦も無く遊べる人が多いけど、こちらの地域の紀元前の話は学校の授業でもほとんどの人が興味を示さない時代・地域の話なので、予備知識が当然ないため、それも長時間のプレイを阻む要素かと思います。
恋愛体質な女(47)

2023年01月05日
CivじゃないCiv。
最近の簡略化されていくCivとは真逆に複雑になっていったCiv。
内政、外国との交渉、周辺部族との関係、国内での政治や人間関係など、やることがたくさんある。
そのため、テンポが悪いのは難点。
私には忙しすぎてクリアまでプレイ時間が取れない。
暇な大学生のときに開発されていれば…
急に、半日もあればクリアできるCiv6をプレイしたくなった。
オススメではあるが、期待しすぎはよくない
今後がたのしみである。
grandgrimoire

2022年11月26日
散々言われてるけど、CivシリーズとCKシリーズを足して2で割ったようなデザイン。
とは言え、ゲーム中の不確定要素がかなり多く、ベターな選択はあってもベストの選択は凄く取りにくい事が、このゲームの難易度を押し上げている。内政か?戦争か?の選択を迫られるのがこの手のゲームのお約束だが、ハッキリ言ってしまうと、中盤までは軍拡を重視するプレイスタイルでないとまともに進まないだろう。内政は二の次、三の次ぐらいのイメージで良いと思う。
Civシリーズと同じような感覚でプレイするとかなり面食らうと思う。感覚的にはフィラクシスというよりパラド系に近いが、パラド以上に戦争寄り。外交で何とかしようにも各人物のステータスが影響してくるので、そこでも歯痒い思いをする人も多いと思う。
面白いゲームであることは間違いないが、万人には勧められない。少なくともCivのような取っつきやすさはない。
あと、文字が凄く小さいです。不満を上げるならまずこの点。洋ゲーあるあるですが、何とかして欲しい所。
TOSHHY

2022年10月06日
ほぼバニラの状態でこの完成度はさすがだと思いました。
結構複雑なルールですがCiv等の経験者なら頭を再構築してある程度の速さで理解すると思います。内政派なため籠って遺産とか建ててたけどどうもそれでは勝てないみたいです。戦争ありきで軍拡していくと上手くいくようす。軍拡していくとスコア勝利となりました。
Civのような繊細な外交ではなく、イベント一つで+80とかの友好度となるため、ある程度大雑把に戦争していても大丈夫なようす。
CKライクな人物制度はとてもダイナミックな展開を引き起こし、賛否あるとは思いますが自分は面白いと思いました。労働者が遺産を建てたり、建物を作るため、Civとは違い、都市の役目、労働者の役目を考えると必要ターンが減ります。グラフックは渋く、とてもセンスが良いと思いました。
だがさすがにDLCを重ねたCiv6の充実には及ばないよう。これからのバージョンアップに期待しています。