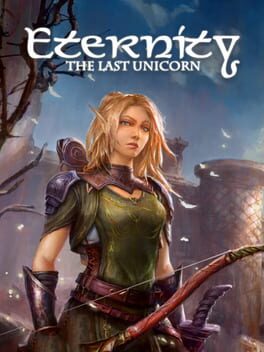Mars 2030
USSに乗ってアームストロング、乗組員 4 名は火星への片道ミッションで生き残らなければなりません。非常にピクセル化されたターミナル グリーン インターフェイスを使用して、手続き的に生成される宇宙の危機に直面します。
みんなのMars 2030の評価・レビュー一覧
Arui Kashiwagi

2017年12月08日
レタス栽培シミュレータ。おまけでスペースシャトル操縦もできる。
(以下まじめなレビュー)
'80年代前半のレトロゲーム、それもカセットテープや雑誌投稿という頒布形態が一般的だった頃を思い出す、昔懐かしいテイストの作品。単にグラフィックがレトロ調というだけではなく、ゲームを構成する文法そのものから古さを感じる。
スペースシャトル乗組員として火星到達を目指すシムなのだが、そのすべてはランダムイベントへの受動的な対応のみで進行する。
多くのイベントの成功率は完全ランダムであり、そこにマネジメント要素は存在しない。若干あるように見えるが実質ない。機器故障や体調不良といったイベントが起きるたびに所定のボタンをポチポチしたり、飛んでくる隕石を上下移動で避けたり、レタスを育てたりすることがプレイヤーの仕事のすべてである。
隕石回避を除けば、ボタンを押すことができた時点でプレイヤーができる介入は終了し、あとはただ成功を祈るのみとなる。
こうして分解して考えると、「要は[b]上下移動とレタスのあるマインドシーカー[/b]ではないのか」という疑念に到達せざるを得ない。
しかしこのシナジーを持たない雑多なアイデアの集合体の中に、まだゲームデザインという概念すら浸透していなかった黎明期のゲーム作りの空気が垣間見える…と思うのは私だけだろうか。
ここで頭に浮かべているのは、思いついた要素を片っ端から INT(RND(1)*N) でトリガしていけばそれだけでなんか盛り沢山な内容に見えた、N88BASIC時代のアマチュアゲームのことである。具体的な名前は思い出せないが、あの頃確かにこんな発想の「ゲーム」がよく作られており、それにワクワクしていたような気がするのだ。
フレーバーの盛り込み方などを見ても、少なくとも作者はけっこう楽しんで作ったであろう雰囲気が伝わってくる。
こういう「おすすめはできないが、個人的に惹かれるところがある作品」はおすすめの方に倒しておくというのが私のレビュー方針なので、今回もそうしておきたい。
…で終わっていればよかったのだが、以上を踏まえてもなお、この作品にはネガティブ票を入れざるを得ない。
1プレイの拘束時間が長すぎるというのが最大の理由。50%地点まで到達したところに唯一のセーブポイントがあるのだが、そこまで最短でも40分。つまりゴールまでは80分以上かかる。それも脳をろくに使わない、緩慢な隕石回避とレタスの水やりだけの80分である。
退屈だからってちょっと飯でも食おうなんて考えると、だいたい目を離した隙に隕石に突っ込んで撃沈している。これで最大40分がロストする。
せめて
・1プレイの所要時間を思い切って1/4~1/8くらいまで短くする
・任意地点でのセーブ機能をつける
・即死イベントをなくし、応答が遅れた時のペナルティも緩和して、半放置前提のゲームとしてデザインし直す
のいずれか一つでも採用されていればだいぶマシになったはず。
実は打ち上げの成功率もランダムで、出目が悪いと開始後10秒でゲームオーバーになったりもするのだが、これは開始直後だからこそ笑って許せるのだ。80分耐え抜いた後の着陸でランダム失敗されては冗談では済まない。
大半の時間は暇、そのくせ操作ミスは許されない。だがミスがなくても最終的に成功するかどうかは運次第…という、人間にはどうにもならない無常さを宇宙飛行の本質として描いた、アート作品として受け止めるのが正しいのだろうか。
暇な時間が大半を占めることは作者も認識しているようで、いつでも遊べるミニゲームがわざわざ二つも用意されており(船内娯楽室に筐体が置かれているという設定)この辺だけはモダンさを感じるが、違うんだ求めてるのはそういうのじゃないんだ…
もっともバスで8時間走り続けるようなゲームと比べればだいぶ有情な部類だとも言える。
(ずれてはいるが)愛が込められた作品であることは確かなので、耐久プレイが苦にならないタイプのレトロゲーマーならば試してみるのも一興かもしれない。
なお不幸にも後年nVidiaから完全同名のVR作品がリリースされてしまったが、関連性はまったくない。