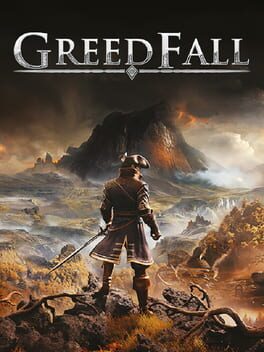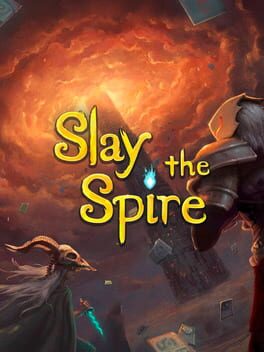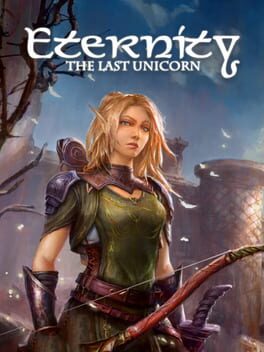Monster Train
地獄は凍りついた。最後に燃え盛る薪を天の力から守り、地獄を復元できるのはあなただけです。 Monster Train は、ローグライク デッキ構築に新しい戦略層をもたらし、防御する 3 つの垂直のプレイ フィールドを備えています。 リリースされたアップデート「Wild Mutations」と「Friends & Foes」が含まれています。 同じプレイスルーはなく、毎回新鮮な挑戦になります。 同じデッキを二度プレイすることはありません。
みんなのMonster Trainの評価・レビュー一覧
Victoriam a3

2020年11月15日
[list]
[*]演出が派手
[*]ユニットのキャラクター性が強い
[*]カードとアーティファクトの組み合わせが豊富
[/list]
なので中毒性が高い。
個人的にはSlay the Spireより断然面白いと思いました。
(そして改めて比べると、やっぱりSlay the Spireの方が面白いと感じました)
日本語化MOD
https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2279315464
[url=shttps://wikiwiki.jp/monstertrain/]日本語Wiki[/url]
Via

2020年10月18日
凍てついた地獄の復活を目指す魔物勢として、天界勢を撃退しつつ種火を載せた機関車で爆走…というやや変わった設定のゲームですが、遊んでいて感じるのは「Roguelite / Deckbuildingが本当に好きorそれらの楽しさを研究した上で、開発者なりの解を一貫して実現している」のだろうということです。
純粋に面白くクオリティも高いため、文字通りSteamレビューの「このゲームをおすすめしますか?:はい」に相当する作品と言えるでしょうか。
・進軍してくる天界勢に種火を破壊されると敗北、という基幹部分はタワーディフェンスを連想しますが、待ち受けて削り殺すTDの感覚とはそれほど近くなく、各層にどういったチームを、どのように攻撃をしのぎつつ配置するか、3+1層のステージによって戦術性に幅と深みを持たせているシステムかと思います。
Run序盤の充実していないデッキ(あるいはそういったコンセプトのビルド)で1層だけ重視して残りはフォローみたいなプレイングも、育ったデッキで3層全てを活かした布陣を作り上げるのも、それぞれの気持ち良さがあります。
・カードをプレイして逐次ダメージを与えていくというより、ターン終了すると一気に多数vs多数を解決する形です。ここがMonster Train唯一の取っつきづらさというか、様々なトリガー能力などが絡んでいると慣れないうちは戦闘の推移が予測しづらいかもしれません。
ただ各ユニットがどれだけダメージを負うか分かりやすく予測値を見せてくれますし、一度覚えてしまえば合理的で楽しい戦闘です(まあ、私は50時間遊んでて未だに「あ、そっち殴ってしまうのか」とかちょくちょくやらかしますが)。カードテキストの記述、ひいてはルール全般もよく整理されており、そういったところにも丁寧な配慮を感じます。
・ヒーローユニットを含む固有カードセットを持つ5種族から、メインとサブとして2つを組み合わせてRunを開始します。近いものといえば、MtGの2色デッキでしょうか(Run中のデッキ構築の柔軟性が高いため、ほぼ1種族特化に絞ることもそれほど難しくはないです)。種族はそれぞれ2つの系統を持つため単純計算で100種類の初期バリエーション、というのは流石に言い過ぎかもしれませんが、ここも飽きの来にくいデザインになってますね。
・各バトル後にボーナスやショップでカード・アーティファクトを獲得していく流れはジャンルの定番ですが、このあたりバランスやインセンティブ設計が巧みで、Monster Trainの「らしさ」でもあると思います。
たとえばツリー状のマップは無く、単に「右は呪文カード強化と種火の回復」「左はランダムイベントとお金獲得」「どちらを選んでもヒーローユニット強化」といった選択肢があるだけです。シンプルすぎるようにも見えますが、実際に遊んでみるとビルドの計画を立てやすく、かといって頑張れば何もかも取れるというわけでもないため、楽しく悩ませてくれるようになっています。
また、全体を通してアーティファクト等に負の効果がほとんど無い点も挙げられます。もちろん負効果を見極めてビルドに適用していくタイプのゲームも間違いなく面白いのですが、一方で欲しい正効果より無難な負効果を重視するようになったり、絶対選ぶ気になれないものが出てきたりと、やや本末転倒を感じてしまうことも無くはありません。
Monster Trainで手に入るのは基本嬉しいものであり(当然バランスは取ってあるので、その分敵が遠慮なく攻撃してきたり、効果が控えめだったりするわけですが)、こういった随所の設計が「運の結果を取り入れて戦略を組み立てる」という、Roguelite / Deckbuildingの核心にきっちり繋がってる印象です。
・全てのカードにアニメーション効果がついていたり、きびきびした挙動を維持しつつ作り込まれたビジュアル面も大きくプレイ感覚に貢献してます。ただ自分側は地獄の魔族ということで、なかなか尖ったデザインが多いのは人を選びそうなところでしょうか(敵の天使は素直に格好良いのでこれはおそらく意図的ですね。もちろん愛嬌あるモンスターもちゃんといるのですが)。
なにしろプレイヤーが最初に選ぶことになるヒーローがスキンヘッドふんどし姿のおっさんというヤバさで、この先愛していけるかかなり不安にさせられました。しかしユニットが育った時の頼もしさ等、結局ゲーム自体に魅力があるとモンスターにも愛着が湧いてくるものです。[strike]たとえスキンヘッドふんどし姿のおっさんでも。[/strike]
Sigetyan

2020年09月27日
点数:85点
タワーディフェンス型Slay the Spire
・良い点
①英語でもやればすぐわかるゲーム性
②ミニオンの配置、スペルの順番等考えることが多くやりがいがある。
③使用キャラクター(リーダー)の数が多くプレイングスタイルが異なりリプレイ性が高い
④難しすぎず簡単すぎない絶妙な難易度
⑤シナジーがハマったときの爽快感
⑥BGMがかっこいい
・悪い点
①強いカード、弱いカードが極端。いらないカードが結構多いので
カードピック時にスキップすることが多々ある。
②リセマラ前提のゲーム性。ゲーム開始時にスターターデッキに加えてランダムで数枚
獲得できるのだがそのカードが微妙ならやり直しをしなければ序盤すら乗り越えられなくなる。
③敵後衛キャラ強すぎ問題。後衛キャラの火力が高く、やっかいな能力持ちが多い。
そのため後衛を除去するスペルが必須になるが陣営によっては前衛にしか攻撃できないスペルしかなかったり
種類が少なかったりするためスターターデッキに入ってない場合カードピックの運が悪いと積む。
④スペル強化強すぎ問題。ゲームを進めるとお金を払ってミニオンを強化するかスペルを強化するか選ぶことができる。
が、その強化がスペル強化一択といっていいほど強力。
悪い点がかなり挙げていますが、全然面白いです。
ローグライト、ローグライク系のゲームは多少ゲーム性が荒いくらいが
面白いですからね。
Slay the Spireの量産型はいっぱい出ていますがこのゲームは
オリジナルに負けないくらいの中毒性と面白さがありますのでオススメです。
chuton

2020年09月13日
Slay the Spireとターン制ユニット戦闘を組み合わせたゲーム。
6つのカードセットがあり、そのうちメインとサブの2つを選んでプレイする。そのゲーム中にはその2セットのカードが出現するようになる。
セットには様々な個性があり、
・火力バフや防御バフが得意なセット
・回復や反射が得意なセット
・ユニットへの直接攻撃魔法と凍傷(StSで言う毒)が得意なセット
・戦闘中にユニットを成長させるのが得意なセット
・ユニットが破壊された時に様々な効果が発動するセット
などがある。それぞれプレイ感が全然違う。
難点としてはせっかくメインとサブの2種類を組み合わせる形なのに、大抵の場合メイン側のカードだけピックしたほうが強くなること。「この効果があっちのセットにあったら強いのにな…」というカードがあんまりないため「これサブいらなくね?」となる。
Slay the Spireと同様に「すごい面白い!」というわけではないのに気づけばだらだらやってる感じのゲーム。
節分の豆まきの時に大して好きでもねぇ豆をフト気づいたら一袋食ってたっつーカンジ。
2x2Size

2020年09月05日
[h1]デッキビルディング×ローグライクな作品史に新たな1ページ
希望の灯火を守るため、列車に侵入してくる敵を迎撃せよ! [/h1]
9/4 Friends & Foes Updateが行われたのを機に投稿。
高い評価を受けた[b]"Slay the Spire" [/b]をはじめとした作品群の成功をきっかけに、カードゲームのデッキ構築要素にローグライクのランダム性を掛け合わせたスタイルのゲームが、人気ジャンルとしての確固たる地位を築きはや数年。まだまだ発展進化の過程にあるこのジャンルにおいて、数多くのフォロワー作品が様々なプラットフォームでリリースされてきました。
単なるクローンにとどまらずしっかりと同ジャンルやカードゲームといった先人から学び、ディフェンス型ゲームに仕上げるという独自軸を打ち出してきた本作、100時間以上遊べる傑出した出来となっておりますぞ。
[b]・概要[/b]
舞台は凍てつき崩壊寸前の地獄、平和を取り戻すべくモンスターは盟約に従い力を合わせ、地獄に一つ残った最後の炎を地獄の心臓部へと送り届けようと列車を走らせる。行く手を阻まんとする天界からの刺客をその力でねじ伏せ突き進め!
4階建ての列車の最上階のPyreを守るために、カードから各階にモンスターを召喚、彼らをスペルで援護し列車に進入してくる敵集団を迎撃、一団の最後に現れるボスを倒せばステージクリア。報酬として得られるカードやアーティファクトを取得し、道中のお店やイベントでデッキを強化圧縮。これを繰り返して8戦目に待ち構える大ボス撃破を目指します。
公式では日本語には対応していませんが、ルールとカードの効果についてはこの種のゲームに慣れ親しんでいるならすんなり読める程度の英語です。
有志日本語化進行中らしいですよ。
以下おすすめポイント
[b]・クランの組み合わせによる多様なプレイ[/b]
本作にはそれぞれ異なった特徴を持つ5種類のクランが用意されており、ゲームを遊んでいくことでその中から2つを自由に組み合わせて選択することになります。ここで選択したクランによってゲームスタート時のデッキとプレイ中に取得できるカードが変化。各クランには約40枚ほどのカードプールがあり、クランに属さないカードも存在。さらにデッキとは別にカードの特殊能力強化などの特性を持つアーティファクトも道中に取得できます。これらがローグライク特有のランダム性と合わさり毎回新鮮で幅広いプレイ感覚をもたらしてくれます。
[b]・長所を伸ばすか短所を補うか、選択式のカードアップグレード[/b]
デッキに組み込んだカードは、道中に存在しているショップでお金を支払うことによりアップグレードを行うことが可能。各カードには2つのスロットが用意されており、ランダムで選出された品ぞろえの中からコストの削減や効果量上昇などを選んで購入強化。また、ショップではデッキ構築ゲームではおなじみとなっているデッキからのカードの削除(つまり圧縮)も有償で行えます。限られたリソースをどうやってデッキ強化につなげるか、悩みどころです。
ゲームスタート時にメインとして選んだクランからは大きなチャンピオンカードが提供されますが、こちらは上記とは違う形でのアップグレードパスを持ちます。彼らはゲームスタート時と3、6戦目のあとに無償で強力なアップグレードを実行可能で、デッキの核となりその方向性を決定します。
カードの取得とアップグレードに圧縮で8戦を勝ち抜けるデッキを作り上げられるかは、プレイヤーの運と選択次第です。
[b]・ルールはやや複雑、しかし見やすい戦闘結果[/b]
多くのカードゲームがそうであるように、プレイを始めた頃は多くのキーワードや能力の数に圧倒されてしまうかもしれません。半面、ほとんどの能力はアイコン化されており、カーソルを合わせることでいつでも詳細を確認できるというプレイしやすさへの配慮も伺えます。遊んでいくうちに自然と慣れていくことでしょう。
戦闘ルールは敵ユニットの攻撃→味方ユニットの攻撃といったもので、基本的にこちらが先制攻撃を受けることになりますので、いかに敵の攻撃を受け流しつつ敵戦力を削り取っていくかが問われるものとなっています。この戦闘結果は手番中にわかりやすく数値で表示されるので煩わしい計算を極力せずに済むのも嬉しい点です。総じてUIもフレンドリーなつくりとなっており遊びやすいものです。
[b]・やりこみ派も満足の大ボリューム[/b]
一度クリアできてもまだまだ終わりじゃありません。進むほどにデッキにお邪魔カードが仕込まれる、敵が強化されるなど段々と過酷になっていく25段階に分かれた難易度が待ち受けています。それらを乗り越えたベテランプレイヤーには特殊な条件下で挑むエキスパートチャレンジがさらに20題。
プレイの記録を閲覧できるログブックでは、どのクランの組み合わせで勝利したかが一目で確認できるようになっており、やりこみプレイヤーも笑顔の内容となっております。また、ここではSteamフレンドの進行状況や最高記録も見ることができます、競い合うのもまた楽し。
[b]・一味違う刺激をもたらすマルチプレイヤーモード[/b]
他ではちょっと見られないものとして、他のプレイヤーと対戦できるHell Rushというモードが実装されています。これは集まったプレイヤーが同じデッキと乱数のもとに一斉に出発、限られた時間の中でハイスコアを競い合うモード。ログやルート選択画面では他のプレイヤーの進行状況が視覚化されて表示されるので、シングルプレイヤーとはまた違ったプレイ感覚で楽しめます。
その他、毎日違った条件下でハイスコアを目指すデイリーチャレンジ、特殊条件を設定して他のプレイヤーとシェアできるモード、さらにシングルプレイヤーのゲーム生成シードを簡単に共有できる機能など、体験を共有できる機能にもかなり力を入れたつくりとなっています。一人でも楽しい、みんなだともっと楽しい。
[b]・総評、このジャンルのゲームが好きならマストバイ![/b]
同ジャンルの中でも上位に位置するであろうゲームプレイの質と量。音楽、アートワークも共に私の中ではかなり好みでした。2か月に1回のペースで行われている無料大型アップデートにより、コンテンツの追加や調整も精力的継続的に行われています。デッキ構築系のゲームとして自信を持ってオススメ。インディーズ作品としてはちょっとお高い価格設定ですが、お値段分以上の価値はありますぜ。
Lukaka

2020年09月04日
プレイ時間が延びたところで追記。
Slay the Spire系の中では今のところ本家に一番迫っている完成度。戦闘がちょっとタワーディフェンスっぽくて本家よりも複雑なのだが、そのぶん戦闘回数が絞ってあり、ビルドと交互に進めていくのでとてもテンポが良い。明らかにHearthStoneを意識したビジュアルも力が入っている。
攻略としては、(特に高ランクにおいては)いかにステータスをスケーリングしていく仕掛けを組み上げるかにかかっており、事前計画がとても重要。パーツさえそろってしまえば、チャンピオンとドラフトユニットのうち1体が必ず初手に来る仕様なのでほぼ計画通りにシステムを構築できる。このあたりはSlay the Spireとは少々勝手が違うところである。
ログブックがとても充実しているのも良いところで、どのクランの組み合わせでどこまで到達したかが一目瞭然なので、全チャンピオン全サブクランの組み合わせでのランク25達成を否が応でも目指したくなる。どう考えてもシナジーがなかったりむしろディスシナジーがあったりする組み合わせの最適解を見つけてクリアできたときはかなりの達成感。
日本語は今のところ非公式MODしかなく導入すると動作が不安定だが、英語のままでもカードやアーティファクトの効果は定型句を一通り理解してしまえば特にプレイには支障なし。Magic: the Gatheringを昔みんな英語でプレイしていたことを考えれば中高生レベルの英語がわかれば大丈夫だろう。
長く楽しめるゲームである。
※さらに追記
全チャンピオン全サブクランでランク25達成したので一区切り。
第一印象を少々改めなければいけない。わりと単調で、飽きるのが早いゲームだった。Slay the Spireは今でもたまーに起動するが、これはもういいかな……という感じ。
たしかにチャンピオン豊富、カードもアーティファクトも豊富だが、どの戦術を採るにしろ結局ボスに殴り勝てる化け物ユニットを1体育て上げるためのシステムをどう構築するかというところに落ち着くので、なんか毎回毎回同じことをやっている気分が拭えないのである。カードの削除が容易なのもこの単調さに拍車をかけている。
もっとも値段分はしっかり楽しめたので買ったことを後悔はしていない。
※DLC後にやりこんだのでさらに追記
DLCに伴う巨弾アップデートで大化けした。なんといってもモンスターを合成できるシステムが面白く、アップデート以前は目当てのドラフトユニットを1体入手できれば後はもうそれに全力を注ぐだけになっていたが、合成できるとなると多数の組み合わせを考慮に入れつつ流れの中での取捨選択を迫られるようになって非常に悩ましい。以前はまず出番のなかったユニットも有効活用できる機会が大幅増。
スペルの特殊アップグレードもコスト2下げや貫通効果や複製など強烈なものばかりで、これによって今まで日の目を見ることがなかった重量級スペルに一気に脚光が当たりプレイの幅が広がった。
最終ボスも攻守ともにかなりのレベルまで鍛え上げなければ突破できないため、最終形を見据えての道中の育成計画に入念な戦略が要求されるように。
全力でおすすめできる良作になった!素晴らしいアップデートをありがとう!
Spooky

2020年09月04日
スコア 80/100
Slay the Spire のフォロワー的なゲーム。基本システムは、ローグライクタワーディフェンス&デッキ構築。現状英語のみで、言語依存はそれなり。平易なテキストなので中学生英語程度。日本語 Wiki に日本語化 Mod あり。
初期デッキを2色から選ぶ様になっていたり(メインとタッチ)、主人公カードのランクアップが選択式だったり、カードのアップグレードがショップで選択式になっていたりと色々意欲的な設計になっている。分かりづらいかもしれないが Slay the Spire のようにある程度型の決まったデッキ構成ではなく、アドリブで柔軟なデッキが組めるデザインとなっている。
また、お約束のアーティファクト(パッシブスキル / MtG のエンチャント)もあったりと基本は押さえてある。カードの種類もそれなりに多い。ゲームのルールが若干ややこしく分かりづらい部分もある。カードシナジーを重視したカードセット&アーティファクトになっているので、カードゲーム自信ニキは楽しめると思う。
少し荒い部分は残るもののアイディアは色々盛りこまれているので面白いゲームには仕上がっていると思う。意欲作ではある。やり込み要素あり。
DDD

2020年08月06日
悪くはないと思うが自分には合わなかった
よく言えば、いろんなデッキタイプでプレイできるシステムなのだが
悪く言えば、使いにくいあるいは好みでないデッキタイプでのクリアを要求される
やらないといつまでもアンロックされないやつ
事前にデッキの方針を決められるというのも、実質カードブロックの選択のようなもの
ブロックごとに効果が極端に尖っているところまではいいが
2つを選ぶ必要があるので、尖り方の噛み合わない組み合わせはつまらない
それがアンロックに絡んでくるのでつらい
1周あたりのプレイ時間が短いのも、人によってはいいと感じるようだが
ようはステージ数≒デッキ強化回数が少ないということなので
強カード・強レリックを引けるかどうかの運ゲー要素が強いとしか感じられなかった
もっとやりこめば面白い点が見えてくるのかもしれないが
そこまで進める気力がなくてリタイア
fai

2020年08月03日
1人プレイ用では最高レベルのカードゲームだと思われるSlay the spireのクローンですが
それだけに収まらない面白さがあります。
多分以下が原因。
・運に左右されにくい
5色のデッキの中から2種を組み合わせて初期デッキを組む+初期に手に入るランダムな5枚のカード+レリック1個、ヒーローカードのカスタマイズ1種でスタートするので攻略の方向性が初期段階である程度決まる(引き直しあり)。なので運が悪くてどうにもならずに終わる、とか結局毎回同じ攻略とかになりにくい。
・インフレ感が気持ちいい。
カード性能をカスタマイズする形式なので「俺の最強カード」みたいなことができる。
ゲームが進むほどヒーローカードは勝手にインフレしていく。
ゲーム難易度もインフレしていく。
・発見がある
コンボがいろいろ作れるし、試してみたくなる。
カードゲーム好きな人は定価で買っても値段分は遊べると思います。
Slay the spire嵌った人にもおすすめ。
teamice2009

2020年07月04日
評価(7点/10)
Slay the spire+タワーディフェンス
良い部分
かっこいいグラフィック
”2色を選んでゲームを開始できる”という ワクワク感
最初にラスボスを知った上でビルドができる
悪い点
カードをパワーアップさせる能力が自由すぎてものすごく強いカードを簡単に作れるうえ、1枚作るとコピーができてしまう。
ある程度簡単な必勝パターンが存在してしまっている
ワクワクしながらプレイできたので今後に期待
chirashi[JP]

2020年06月26日
最高難易度をクリアしました。
カードのアプグレができる、カード2枚削除マスやカード複製マスが1ゲーム中にそれぞれ数回利用できるなど
自分の作りたいデッキを作りやすくなっている。
StSほど厳しくないのでお気軽にどうぞ。
tap

2020年06月01日
モンスターをカードから召喚して、
ディフェンス対象を守りきるタワーディフェンスのようなゲーム。
5種類の陣営(初期選択できるのは2種類)から、メインの陣営とサブの陣営を1個ずつ選べるシステム。
選んで遊んだ陣営ごとに経験値が入り、新しいカードやアーティファクトがアンロックされていく。
継続的に効果を発揮するアーティファクトがこのゲームでは一番運の要素が強く、プレイ中毎回数種類が手に入るが、
かなり種類が多いため、リプレイ性が高い。
カードゲームだが、自分でデッキを構築する必要はない。
初期手札は毎回固定+プレイ中に取捨選択していく感じ。
陣営のLv上げは各陣営10Lvまでやり込める。
難易度選択ないじゃん?と思ったあなた、COVENANTというシステムでクリアするごとに上の難易度に挑戦できる。
なので難易度26段階を選択可能。
今のところ16時間プレイして、Lv上げやアーティファクト集め、難易度開放はまだ1/3も終わっていない。
ちなみに最初に選べる2つの陣営はあまり癖が無い代わりにあまり面白みもないので注意。
Rysk

2020年05月30日
結論から言うと非常に面白いです!
Slay the Spireにインスパイアされた数々の作品の中でも現状トップです。
敵の先制攻撃だが、スペルは先に使えるというのがより面白さを引き立てています。
ゲームシステムの特徴だけじゃなく、グラフィックもかなり頑張っていると思います。
殴り殴られモーション有り、カード内もアニメーション、その他、
ゴールデンカード報酬があったりログブックの雰囲気はHearthstoneっぽさも感じます。
気になるところは、
5つのクランと全てのカードの解禁に結構時間がかかります。
また極端に相性が悪いクランの組み合わせがあります。
StSよりルールが複雑なので勝ち筋が見えにくいです。
sasasa

2020年05月28日
優秀なデッキビルディング
天使たちによって炎を消された地獄を舞台に、最後の炎を迫りくる天使どもから守り抜き再び炎を灯せ!
特徴的なのは、バトルフィールドが4階層になっており、敵は1階層から侵入してきて4階の最後の炎へと進撃する。
各階層は、それぞれ配置できるモンスターのコストが設定されており、複数の敵・味方に効果があるスペルは各階層ごとに適用されるため、各バトルにおいて味方の効果的な配置を手札と相談しながら進めていくため、毎回同じことの繰り返しにはならないためリプレイ性が高い。レベルが上がるにつれて使えるカードが増え、それによりどんどん戦術が広がっていって非常に楽しい。
また、カード同士のシナジーを重視しており、単に強いカードを並べるよりもシナジーを考えたほうが勝ちやすい点はプレイしていて悩ましくも楽しい。
デッキもカスタムの幅も広く、種族の組み合わせ、カードのアップグレード、アーティファクトの収集、お金の収集等やれることの幅が非常に広い。
ただし、アーティストについて強力なものが多い一方でハズレ枠や使えないものもそこそこあるので運要素が高い。
全体的に完成度バランスも良く、運と戦略のバランスも良いと感じた。
唯一の不満点としては、初期に勝手に作られる5枚のスペルカードが非選択式のためなので、初期手札のバランスが著しく悪いと感じた。更に、序盤ではモンスターカードを得られるチャンスが少ないため、チャンピオンによってはそこそこ事故死する。
そのため、アップデートでドラフト式にしてほしい。
hizlimy

2020年05月27日
カードビルド、アーティファクトなどSlay the Spire(以下StS)に似ている部分はありますが、実際やってみるとゲーム性はかなり異なります。
・ステージが短い
StSの1面でクリアくらいの短さです。
手軽に遊ぶにはいいかもしれませんが、デッキビルドの楽しみが薄くなっています。
・タワーディフェンス型ゲーム
ここがStSとの大きな違いだと思います。
毎ステージ、同じ敵からの攻撃を数ターン続けて受ける形になります。正直、単調な感じがして飽きます。
・周回について
StSでいうところのアセンションモードがありますが、クリアまでが短いので
カードが全部揃わないまま何回も同じ周回を回る必要があります。
・戦略性
割と大雑把なゲームという印象があります。
戦略性はStSと比べるとかなり低いです。
・総括
StSのようなスルメ感が無く、すぐ飽きてしまいました。
つまらなくは無いと思いますが。
今後のアップデートに期待します。
ThePrime

2020年05月25日
StSライクなデッキ構築型と、独自の戦闘設計を組み合わせた意欲作
戦闘はユニットを召喚し突き合せるタワーディフェンスやMTGのような設計になっている
全クラン(デッキベース)解放し使用したが、相当面白いのでお勧め
難点は少々戦闘の時間が長くなることくらい・・・
良い点とゲーム概要はいっぱいあるのでこれから解説
カードはユニットと魔法があり、さらに常時効果のアーティファクトがある
カードのコンボシナジーが強く、組み合わせることで敵を圧倒する戦略が組める
開始時に2種のクラン(デッキベース)を選ぶ
各クランは38種のカードで構成され、各カード有効性が確保されているため、
ランダムでありながらも(高難度でなければ)戦略次第で勝つことが可能になっている
全体的な戦闘設計が秀逸で、かつカードに好きなカスタムを乗せることで、
強力な敵をそれ以上に凶悪な手段で叩き潰せる
戦闘数は8回で固定で毎回雑魚が8フェーズ程とボスが進行してくる
また3,6,8戦で大ボスになる
戦闘は、雑魚とボスで若干戦略が変わり、
雑魚は1ターンで階層を1つ上がるが、ボスは階層を全滅させるまで戦うことになる
大ボスはさらに侵攻前にも外からいろいろしてくるし攻撃も可能
[h1] ゲーム内に仕込まれた背反設計が秀逸 [/h1]
・基本的には3層1ターンずつで進行する雑魚をしのげる火力が必須だが、
このタイプのゲームには珍しく、敵が先制で動くため火力正義だと殺される
・後衛に厄介なバフデバフを付けるキャラが配置されるが、
通常のモンスターは前から順にしか殺せないため、魔法や特殊な攻撃で後衛を殺す手段も必要
・戦闘開始時にチャレンジモードが選べる 相当厄介な効果が付くが報酬が増える
ユニットやアーティファクトや金が増える・・・増え方も先に確認できる
・イベントの多くは、利点と問題点がセットになっている(ライフが減るけど金が増えるとか)
何もしない選択があるのでコントロール可能
・全マップが最初に見渡せ、分岐の選択は常に2択でセット効果を選べる
計画して進むもよし、状況に合わせて選ぶも良し
・賛否はあるが戦闘単位なら最初からやり直せる方法がある
ミスをカバーできなくもない (ただしチャレンジは決定済みなので取り消したり増やしたりできない)
[h1] クラン紹介[/h1]
・HellHorned
強力な攻撃ユニットDaemonと、召喚時効果を持つ弱ユニットImpをもつ
クラン的バフ MultiStrike(複数回攻撃) Rage(漸減する攻撃強化) Armor(追加HP)
能力的にはStrike(攻撃時発動)やSlay(殺害時発動)
・Awoken
防御面に強いユニットHollowが特徴的
クラン的バフ Spike(反撃ダメージ) Regen(漸減するターン終了時回復) Quick(先制攻撃)
能力的には Rejuvenate(回復時発動)やRevenge(被攻撃時発動)
・StygianGuard
魔法攻撃が特徴的
クラン的バフよりデバフ SpellWeakness(呪文ダメージ増加) FrostBite(漸減するターン終了時ダメージ)
能力的には Icant(呪文発同時発動)やOffering(このカードが捨てられるとき発動)
・Umbra
食べられるユニットMoselが特徴的
クラン的バフ Trample(貫通攻撃) EmberDrain(Emberの回復量が減るデバフ)
能力的には Eaten(ターン終了時、Eatenでない先頭ユニットに食べられて死んで発動)
Gorge(自分が食べたら発動) フロアのサイズ拡張など
・MeltingRemnant
ターン経過で死ぬユニットが特徴的
クラン的バフ Burnout(スタック数がなくなると死ぬデバフ) Stelth(通常攻撃されない)
能力的にはHervest(誰かが死んだら発動) Reform(死んだユニットにBurnoutと強化を付与し復活)
Extinguish(死亡時発動) 金を稼ぐ効果
[h1] コンボ例[/h1]
・Sweep(全体攻撃)+Quick(先制攻撃)で脆弱な後衛を先に薙ぎ払う
・高い攻撃力+MultiStrike(複数回攻撃)やTrample(貫通攻撃)で前衛をつぶしながら後衛も攻撃
・HoldOver(呪文使用後デッキトップに移動)+コスト減で毎ターン無料の呪文
・HoldOverの強力呪文とHoldOverのカードを引く呪文で、毎ターン2回強力呪文
・上記と合わせIncant(呪文発同時発動)ユニットで効果を多重適用
・強制移動時にDaze(1ターン行動停止)x3のAF+強制移動スペルで完全無効化
・Endress(死亡時デッキトップに移動)+召喚時効果や生贄効果で毎ターン無料の効果と肉盾
・Mosel(ターン終了時に死亡し効果発動するユニット)と、Hervest(誰かが死亡時に発動)で効果を多重適用
・第1層(死にやすい)に大量のStelth(攻撃されない)をつけ雑魚では安全性を確保、
ボスでは「全滅するまで戦う」機能を利用し大量攻撃
私が室長です。

2020年05月24日
StSから面白い要素を抽出して、独自要素を加えつつ再構成したようなゲーム。ゲームシステムは複雑になっているので、万人向けではないが、StSに飽きた人にはほどよい塩梅かもしれない。
良い点
・グラフィック、音楽がともに90点くらいの良い仕上がり。
・カード効果が個性的。複雑なゲームシステムを活かした、ユニークなカードデザインばかり。
悪い点
・ボスラッシュのような感じで1回の戦闘が長く、カードを引くフェーズが少ないので、引きでビルドの構成が決まりがち。冗長な戦闘が無いので利点でもある。
・最初はカードの種類が少なく思える。ある程度アンロックするとビルドの幅が広がる。
もう少し取っつきやすくしない限り名作には至らないが、逆に言えば、調整次第ではローグライク史上、StS以来のヒット作にもなり得る期待の一作。日本語対応さえすれば、DCG界隈で絶対に流行ると断言できる。
nami-he

2020年05月24日
Slay the Spire(SoS)はまった人です。
SoSとの主な違いは以下のとおりです。ルールは若干複雑になりますが、さらに奥深い戦略が必要になり、非常に面白いです。
・タワーディフェンス要素が加わる。(列車の1階部分から敵が侵入し、4階部分の列車のコアがやられたらゲームオーバー)
・一人の主人公で進んでいくのではなく、カードからユニットを召喚して戦闘(チャンピオンは5種類から選択)
・デッキ属性5種類から2種類を選んで開始
独特なデッキ属性5種類、チャンピオン5種類(最初は2つのみ解放)、レベルは25段階まであり、やりこみ要素も充実していそうです。
以下に、簡単な説明動画(ストリーミングですが)おいています
https://youtu.be/Gi0jd110x34
関心ある方はどうぞ!
地縛神ポンタリウス

2020年05月24日
流行りのSlaytheSpireライクだが本質はタワーディフェンス
気付くと時間が溶けている魔性のゲーム
スペルやユニットをアップグレードして自分だけの最強デッキを作ろう!
Tolein

2020年05月24日
4層目のクリスタルを1層から順に登ってくる敵を倒して守るカードゲーム
もうこれがArtifact 2.0でいいよ
タイムアタック等のPvPもあるし
TapiokaSAMURAI

2020年05月24日
シングルプレイをクリアしました。が、やっぱり、カードゲームをあまりしない人や英語が苦手な人がプレイすると、プレイ中によくわからない場面がでてきてそこで詰まって投げそうな感じがします。
ただゲーム自体はかなり面白いゲームだと思うので、カードゲームをあまりプレイしない人にもおすすめかと。
このゲームは日本語が無い為、
日本語翻訳をした動画を作ってみました。(翻訳は適当です)
https://www.youtube.com/watch?v=UaPwYHe20Pg
追記、プレイ画面の見方も解説もしてみました。
https://hokkori-bekarin.com/steam/archives/688
英語があまり読めない人でもこれで画面の見方が分かると思います。
esehara

2020年05月23日
【2020/05/24でのレビュー】
『Slay the Spire』を持っていると20%オフということなので購入。
モンスターを詰んだ列車が爆走する中、天使たちが妨害しにやってくるので、手札を駆使して追い払うデッキビルディング・カードゲームだ。特徴としては、一回限りのモンスターカードを使って、手下となるモンスターを召喚したり、あるいは相手を直接攻撃したり、モンスターを強化したりするスペルカードを駆使して、攻めて来る相手をなぎ倒していく、といったデッキビルディングかつ、何処となく軽いタワーディフェンスとなっている。また、これらのモンスターはそれぞれ「クラン」というかテーマが存在しており、五つの中から組み合わせてデッキを組むという形で、この組み合わせを考えるだけでも楽しいし、それなりに特色があるので面白い。
カードゲームにおいて、確かにモンスターを召喚したりするのは、花形である。それは、マジック・ザ・ギャザリングから変わらないものだと思う。かくいう俺もモンスターどもは大好きだ……。ビジュアルも、音楽も、それなりに良い。ゲームもそこそこ遊べる。優等生的に手堅くまとまっているという感じである。一応「お薦め」にはしたんだけど、まだ何か……もうちょっと……味付けが欲しいなと思ってしまうところがある。
良いところとしては、ステージが短いことである。考えても見れば、パーマデスという「死んだら全部レベルが失って最初から」というシステムの癖に、やたらと長い時間遊ばせては、全然モノが揃わず、案の定死んでがっかりするというゲームが多いことを考えると、この短さは好きである。また、マルチプレイ(単なるスピードランなのだが)というシステムとの相性としてもいいと思う。しかし、同時にそれはコンテンツの少なさに繋がっているわけで、それは今後の更新によるものだろう。
ゲームバランス的には、まだリリース最初の頃なだけあって、他の人も言及しているようにまだまだ粗い。各モンスターのデッキ毎に「チャンピオン」が存在しているのだが、明らかに「弱い能力」と「強い能力」が存在している。場合によっては、そのテーマの良さを潰しかねない能力も存在している。これも恐らく今後の更新によってバランスがとられると思う。
マルチプレイヤーもまた少し面白くない。前に書いたとおり、これは単なる複数人によるスピードランなのだが、バトルごとに時間制限があり、それを超えると手札が使えないまま、自動的にバトルが処理されていく。しかしカードゲームというのは「少し立ち止まって考える」のと「流れがわかっているので機械的に処理する」という二つのパターンがあるわけで、さすがにゲーム性とマッチしていないような気がする。リワークか、あるいはもう少しギミックが必要な印象を受ける(「皆が死ぬのを待つ」という卑怯な戦略を潰したいのはわかるのだが……)。
確かにオススメはするものの、まだ出来としては「7点」といったところだと思う。色々なギミックはあるのだけれど、やはりどうしても既存のデッキビルディングという枠からは抜けだせていないように思う。逆に言うならば、そういう「優等生的な」ゲームとしては、手堅くまとまっている。余程こういうゲームが好きでない限り、今は急いで買う必要もたぶんない。正直、「悪くはないけれど更新待ちの要素が多い」というところが目立つ。
とはいえ、ストリーマーがなんか宣伝したり、『Slay the Spire』の開発者とイベントしたりということで、出だしは順調なので、一年か二年くらいかけて成長させていけるとは思う。なので、ライブラリの肥やしとして見守る分にはちょうど良いように思う。
mutipoyo

2020年05月23日
ずっとやり続けてる気にならないけど、何となく1日1回やりたくなるようなゲーム。
DEMOのときからやってるけど、DEMOの時に比べ難易度がだいぶ下がってる。
運が悪いと序盤で死ぬし、運が良いとクリアできたりなので、1日の運勢を占うのにある意味良いかもしれない。
自分にとっての理想の流れを引き寄せるために延々とやってしまう。
脳みそが溶ける。
ネイティー_NEET

2020年05月22日
天使軍のせいでヒエッヒエされた地獄を暖める為に遠くから機関車で燃料を運ぶ・・・そんなコスモクリーナー的なストーリー
だが、いつも天使軍がヒャッハー乗り込んでくると分かってるのに、悪魔達は毎度ザルな警備で苦労させられるローグライク系デッキビルドゲー
風変りなシステムと戦闘で、「Slay the Spire」クローンに飽きたプレイヤーには目新しいのでそこそこ、楽しい。
だが、ハッキリ言うと・・・まあ、バランスが悪いと言うのか粗が多いので正直オススメか微妙。
2020/07/24 追記
アップデートで更にクソ化
やる価値はない位には落ちぶれました。
ここから悪い点をザっと書き出すから、読むの面倒なら購入自体を様子見しろよ
・システムが特殊で、敷居が高め
・カードの効果も英語読めないとツライ、敵味方どちらもバフ・デバフの色々と効果が多い
・良くも悪くも敵味方問わず、モンスターを選択してカードを使える。慣れない内は操作ミスで敵に回復使っちゃうぜ
・ゲームのテンポは遅くて悪い、ゲームスピード上げてもストラテジー、タワーデュフェンス要素もあるせいで無駄に時間が掛かる
・カード同士のシナジーが激薄、特定のカード同士でしか最大の効果を発揮できないモノばかりで、組み合わせがテンプレ化まったなし。デッキ構築の楽しさが低い。
・そのうえで、コンボに手間が掛かるカードばかり
・なので、ゲーム開始時に強制的に2種族選ばされて混生デッキを作らされるのだが、運が悪けりゃロクなデッキが出来ない
・メインに据えたデッキにチャンピオンと呼ばれる固定モンスターユニットが居るのだが、これも特定のイベントで強化できるが、好きに強化できない。外れの強化が出たらリセットまったなし。
・産廃カード多数、またはそれらの上位互換のカードが多い
・アーティファクトと呼ばれる、カードとは関係なくバフが貰えるアイテムがあるが、これも効果があっても無くてもゲームに影響しないくらい弱い、その上で確立で発生すると言うモノばかりで、デッキ構築を左右する要因になってない。
・逆に強力すぎるアーティファクトもある、(無限インプ生成やアーマー生成時に無条件で+4など)
・アンロック要素が作業。そして強いカードは全て最初はアンロックしてるぜ
・第三のデッキ「Stygian Guard」が強すぎる・・・、まあ上に書いたように他の種類のデッキが手間が掛かって弱すぎるだけだが・・・
・一部ラスボスの性能が頭オカシイ、ゲーム開始時にラストに戦えるボスが決定されるのだが・・・ソイツが出たら即リスタートで良い。無条件でデッキ破壊されるとかやってられん
・手札を増やす方法がほぼないし、ドローカードが少なすぎる。なので露骨にゲーム側に手札操作されてる感がハンパナイ。
・イベントでもらえる特殊カード達がどれも貧弱すぎる、イベント見てハズレが出たならスキップ余裕
・システム上、自分は全て後攻なので、序盤でいいモンスターユニット貰えないと、燃料届ける気ないだろとツッコみたくなる
・システム上、自分は全て後攻なので、自分に有益なバフを掛けづらく、掛ける前にモンスターやられたり、掛けても先攻のモンスターに打ち消されたりして、イラっとする場面が多々ある。
・画面が非常に狭いし見辛い、選んだデッキよっちゃモンスター数が多くなるのでクリック選択がしづらい。
・マルチアタックというモンスターの攻撃回数を増やすスキルがぶっ壊れ性能
・それでいて、ほぼマルチアタック前提のゲーム難易度
・そしてそのマルチアタック含め、いい強化をゲーム中に点在するショップで引き当てれなければオワコンだぜ
・だけど、好きに強化は出来ない。攻撃・ライフ強化スペルは露骨に制限されて最初はクソゲーだろと感じる(強化する手段はある)
・対戦もあるが・・・トップの人間しか有利になる要素しかなく、巻き返す要素もゼロなので戦闘開始時にトップ取れなきゃそこで負けなので、クソつまんない
・新しく追加された要素もこのゲームを死ぬほどやり込んだ狂信的なプレイヤーしか体験できないようなアンロックの条件でやる価値が無い・・・どれだけのプレイヤーがランク25に到達したか実績の達成率見てみろよ開発・・・
・役に立たないカードばかりなのに、カードを更に全体的に弱体化とコストアップするという頭が沸いたバランス調整・・・
デッキビルディング系の楽しさは無くなり、タワーディフェンスっぽい構築どころか完全にパズルゲーと言うほどに手数が決められるアホ臭さ・・・それに今まで以上にカード同士のコンボが無さ過ぎて無味
もう「Stygian Guard」すらもオワコン、バカとしか言いようがないクソゲ。
ska

2020年05月22日
スレイザスパイア系のゲームは色々やってきたが、これが一番好き。
非常にテンポが良く、操作も快適。
システムが分かりやすく、カードデッキの強化が戦闘にすぐに反映されるので
取捨選択の楽しみがある。
日本語はないが、直感的にプレイできるので問題ないだろう。
1回のプレイ時間は1時間かからないぐらい。
stsのアセンションのように、難易度を上げていくシステムもある。
初期デッキに多少のランダム性があり、デッキ全体をバフするアーティファクトの入手や
どのカードをどのように強化するかでプレイに幅が出るようになっている。
初期キャラクターはほどよい段階でアンロックされていくので、
次はこういうビルドを試そうかな、と考える楽しさがある。
非常によく作られていて、これといったアラがない。
「またstsみたいなのか…」って思う人は是非プレイしてみてほしい。
強いて欠点を挙げるなら、ぶっ壊れているアーティファクトはないので
over dungeonのようにハチャメチャなビルドは組めないというところか。