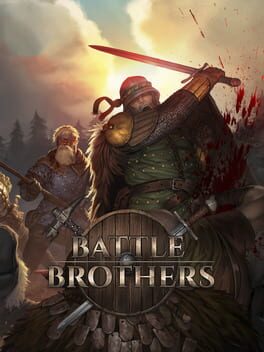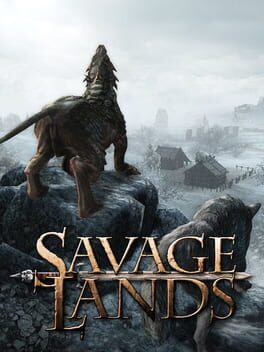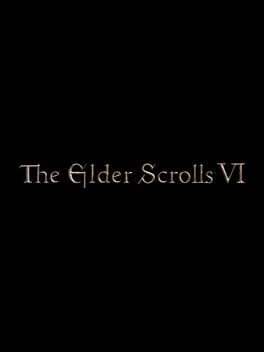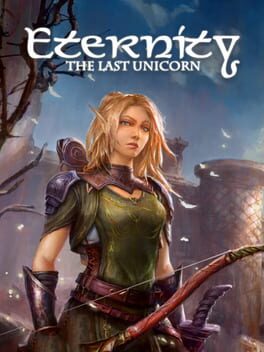Tenderfoot Tactics
元素魔法が自然界と相互作用して複雑な結果をもたらす戦術 RPG です。
みんなのTenderfoot Tacticsの評価・レビュー一覧
esehara

2021年02月26日
[h1]幻想的で神秘的なビジュアル・音楽を持つ、スクウェア系タクティクスの子供[/h1]
過去にスクウェアは代表的な二つの「シミュレーション」を出している。それは『タクティクスオウガ』と『ファイナルファンタジータクティクス』である。前者で確立されたスタイルは後者で成長し、一つのスタイルとして定着し、ファンや影響されたゲームが堪えない隠れた人気ゲームとなっている。
本作もそのフォロワーの一人だとも言える。グリッド型の高低差あるフィールドをユニットが移動し、そして敵を撃破しながらユニットを成長させていく。そして、成長しきると別の職業に転職することができる。しかし遠距離攻撃ばかりだと貧弱だし、近距離攻撃だと遠くからチクチクやられる。ヒーラーがいなければ持久戦にやられるし、範囲攻撃ができる魔道士がいなければ数に圧倒されたときに不利だ。従って、出来るだけバランスを取りながら成長させていく必要がある。
だが、本作の最大の特徴は「その世界を表現した、抽象的で神秘的なビジュアルとミュージック」にあるだろう。そして、それを出来るだけ妨げないようにしながら、シンプルでカジュアルに仕掛けつつも、ひねりを加えて出来るだけ退屈しないようにしている……そういう形になるだろう。
[h1]バトルはシンプルでありつつも、ベストを尽くすとなると難しい[/h1]
実際、ユニットのステータスを見ると、驚くほどパラメーターが無いことに気がつくだろう。ユニットには「体力と攻撃力」だけである(正確に言えば、これに風や水といった属性値が付く)。従って、防御力も存在しないし、命中率も存在しない。なので、攻撃をすれば当たる。
多くのシミュレーションでは「命中率」が採用されているが、しかしこれらはプレイヤーの苛立ちのもとになっていた印象もある。「95%」というほぼ必中の確立で外れて、戦線が崩れるといった経験をした人は何人もいるはずだ。そういった「苛立ち」から解放されているので、「どのユニットを動かし、どういう攻撃をするか」に集中できるところは良いところだ(外れたときのことを気にしなくて良い)。
またそれだけだとあまりにもシンプルすぎるため「攻撃されると士気が挫かれて行動が遅くなる」というシステムも採用されている(敵によっては「行動順が早くなる」のもいる)。例えば、目の前に戦士と魔法使いがいて、戦士の体力は減っているけれども、魔道士が次のターンに行動するので厄介だな……と思ったら、魔道士を攻撃して、その行動を遅らせることは可能だ。
一方で本作の特徴となっている「攻撃による地形変化」の部分なのだが……正直、これに関しては深さを感じることはなかった。というのは、地形を利用してまで撃破するといったことを考慮する余裕はなく、どちらかといえば「範囲攻撃したついでに地形が変化する」という印象であるので、あまり期待しすぎるのは良くないだろうとは思う。高低差はほぼ移動のときに意識するだけで、近接攻撃は当たり前のように、高い地形に対してもあたったりする。
しかしこれらにも関わらず、ユニットを出来るだけ生き延びさせるのには苦労する。ユニットが死んでも特段ペナルティは存在しないのだが、経験値が受け取れなかったりするので、出来るだけ生き延びさせたほうがよい。この辺りの「勝つのは案外簡単だが、ベストになると難しい」という、程よいバランスのように感じる。敵キャラもだんだんと一癖や二癖もあるキャラが増えるので、そこも良いところだと思う。
[h1]あまり良くないユーザーエクスペリエンス[/h1]
優れたビジュアルデザイナーが、優れたUIデザイナーではないというのは、このゲームでも当てはまる。とはいえ、十分に整理されているほうではあるのだが、しかしやはりそれでもやりずらさを覚えることはあるだろう。
例えば、シミュレーションに期待されるべき「移動のキャンセル」というのは、このゲームには恐らく存在していない。また、このゲームは回復も攻撃も「味方・敵関係なしに」発動できる。この二つと相まって、割と誤操作を起こしやすく、それで戦線がひっくり返ることはないものの、多少不利になってイライラすることがある。またその結果として「行動してみたら攻撃が射程範囲ではなかった」ということもあり、この点は割と不便ではある。
[h1]ミニマップを無くしてあえて不便にしている冒険[/h1]
本作はオープンワールドを謳っており、言い換えると要は「何処から旅しても良い」ということになる。しかし、このゲームにはミニマップが存在していない。いや「地図」自体は存在しているのだが、本当に地図というだけで、何処にいるか、そして何があるのかということは「地図」と周辺の風景を照らし合わせることになる。
さらに面倒なことに、このゲームは「地図」が複数枚ある。つまり、地図によって情報が分散しており、目的に応じて地図を選ぶ必要がある。これ自体は良いとも悪いとも言えず、一つのコンセプトとして合っているかどうかだろう。だが、方向音痴であったり、地図を読むのが苦手な人は果てしなく苦痛になる作業であると思う。
一方で、実際のフィールドは「ウォーキングシミュレーター」と表現するのが十分なくらいそっけないものになっている。画像は綺麗ではあるのだが、何か驚くものが出てきたり、あるいは興味を惹くものはそれほど出てくるわけではなく、のっぺりした無個性な大地をひたすら歩き回るということのほうが多い。草木は生えてはいるが、砂漠を歩いているかと思うくらい密度がないので、魅了はされるがワクワクしないというところはある。
一応、霧が立ち込めているフィールドの敵を倒したり、あるいは「Fae Weed(妖精の葉)」を掴むことで、その霧を浄化していくというのはあるのだが……この辺りは単純に散歩が好きな人じゃないと、延々と地図を読み解く作業と相まって、正直退屈な気持ちになるとは思う。良くも悪くも「ビジュアルイメージ通り」の尖りようとも言える。
[h1]総評・コンセプチュアルだが、十分にゲームとして楽しめる良作[/h1]
ビジュアルセンスや、ミュージックセンスはとても良く、完成度の高い没入感があるし、バトルシステムは「良くも悪くも標準的」で、普通に楽しく遊べるが、何かもう少し味が欲しくなる感じもある。しかし、問題はない。
問題はフィールド探索部分の、極端にコンセプトが先行している部分であると思う。あまりにも最近のゲームらしくない不親切さがあるだろう。とはいえ、もしビジュアルイメージが自分好みであり、なおかつ英語が苦にならなければプレイする価値は十分にあると思う。
「インディーズゲームとして、自分達が作りたいものを作りました」という意味では高い水準・品質を持っているとは思うし、動画や画像を見てそのイメージに惚れたというのならば、このゲームはその初見を裏切らない鮮やかな世界を描き出していることは間違いないと思う。